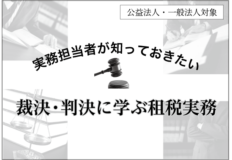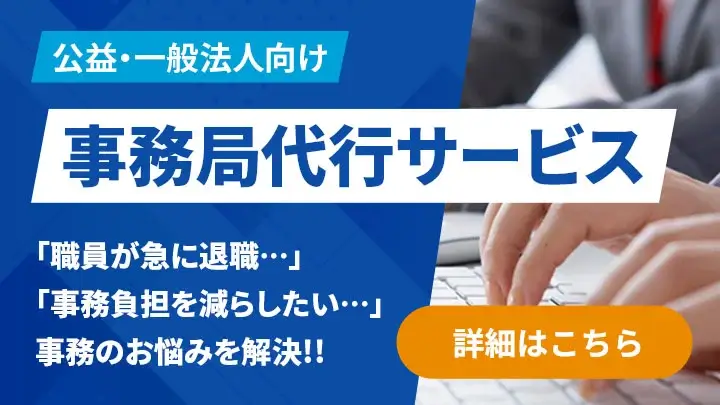明治以来初めての大改正!! 担当者が知っておくべき民法改正のポイント
2021年03月02日

熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
(くまがい・のりかず 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
明治29年(1896年)の制定以来120年ぶりに大幅な改正が行われることになった民法ー。200項目以上にわたる改正事項の中から要点を絞って解説する。
はじめに
既に各種メディアで報道されているとおり、現在開会中の第189回通常国会に「民法の一部を改正する法律案」が提出されている。この民法改正は、民法典のうちの債権法分野及びそれに関連する条文を大幅に見直しの対象としているものであり、債権法分野の改正としては、明治時代に民法が制定されて以来の大改正である。もっとも、弁護士その他の「士業」は別にして、私たちの日常の経済活動で民法を特別に意識しなくても支障がないのと同様、改正された民法の詳細を知っていないからといって日常の経済活動に大きな影響が及ぶことはない。したがって、公益・一般法人にとって民法改正が必須の知識であるとまではいえない(一般法人法の改正の方が知識としては重要であろう。)。ただ、紛争が生じた場合には、デフォルトルールとして民法の規律は重要な意味を持つ。「債権法」分野は、契約その他社会・経済生活全般に及ぶものであり、公益・一般法人にとっても無関係ではありえない。その意味では、リスク管理の観点からは、民法改正についてのある程度の知識はあった方がよい。
本稿は、200項目以上にわたる民法改正事項の中から、与えられた紙幅という制約の中で、公益・一般法人にも関係ある改正事項のうちの一部につき、簡単に解説するものである。
Ⅰ なぜ民法改正なのか
民法典は、取引のルールや所有権のルール等だけではなく、親族や相続等、私たちの生活全般に関わる様々な範囲に及ぶルールを定めている法典である。しかし、明治29年(1896年)に制定されて以来、第二次世界大戦後に親族・相続分野で大月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。

公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。