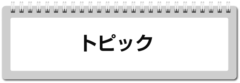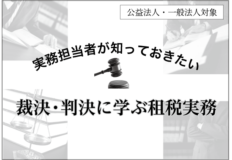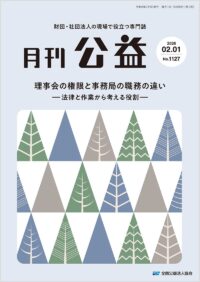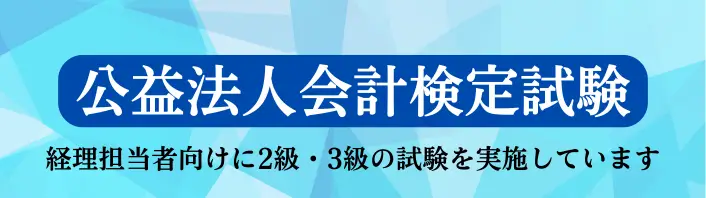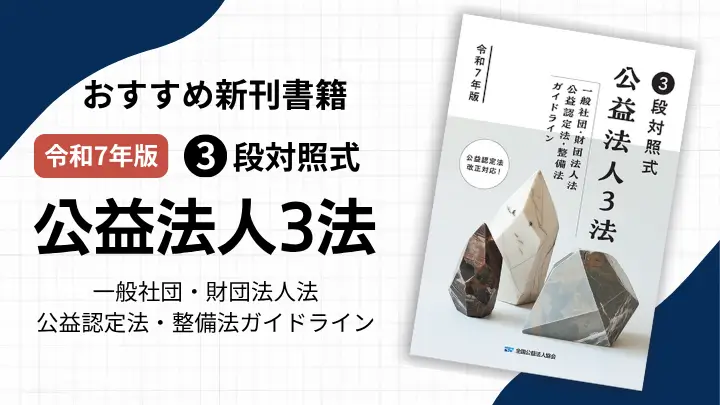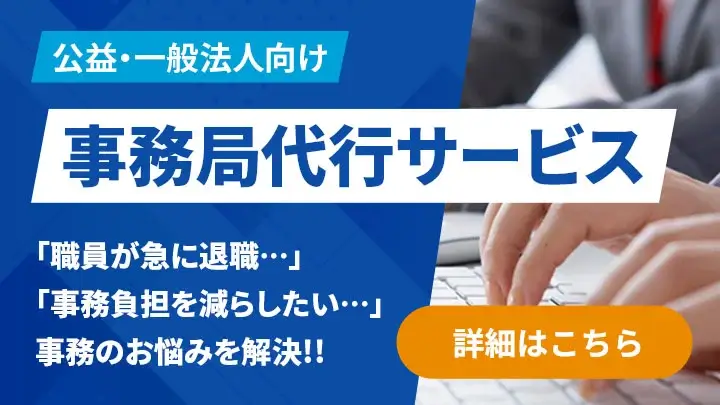使途不特定財産(遊休財産)と控除対象財産
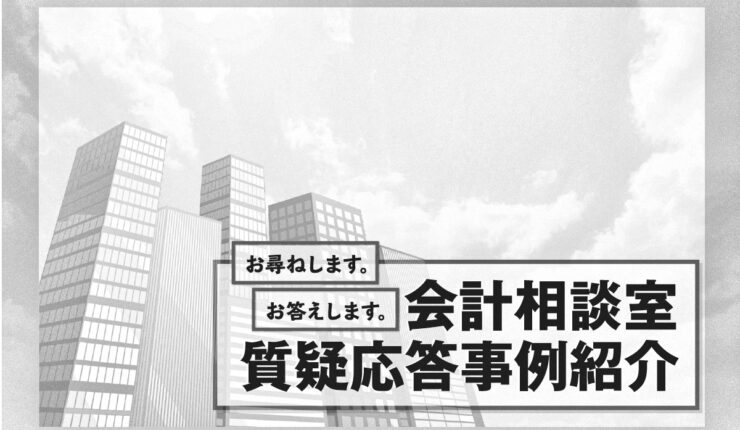
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士)
一昨年より公益財団法人の財務・経理担当になりました。これまで公益認定の財務基準で収支相償は概ねクリアしてきたものの、遊休財産は、保有制限額を超過したこともあったと聞きました。旧制度での遊休財産につき、ある程度理解したと思ったところで、新制度が施行され、戸惑っています。制度変更を踏まえて対応策をご教示ください。
1 使途不特定財産とその保有上限額
旧制度の遊休財産額は、新制度で「使途不特定財産額」に名称が改められました。その額は、法人の純資産の額から、負債(基金を含む)の額、控除対象財産の額(対応負債の額を除く)、公益目的事業継続予備財産の額を控除し算出します(認定規則36条2項)。なお、公益目的事業継続予備財産は、災害等の予見し難い事由に対応し、公益目的事業の継続に必要となる公益目的事業財産(認定法16条2項)で、新制度から控除対象とされました。
使途不特定財産の保有上限額の基準となる1年相当分の公益目的事業費は、旧制度の「当該事業年度の公益目的事業費」から、「前事業年度までの5年間の公益目的事業費の平均額」に改められました。なお、その理由を明示した上で、当該事業年度又は前事業年度の公益目的事業費の選択も可能です。
2 保有上限額超過の原因
保有上限額の超過(使途不特定財産額-保有上限額>0)の発生要因は次のとおりです。
⑴ 純資産額の増加
収益の増加又は事業費・管理費の減少で剰余が生ずると純資産が増加し、使途不特定財産額の増加要因となります。公益目的事業で収支相償を満たしていても、収益事業等や法人会計で公益目的事業の赤字を上回る黒字が発生すると、使途不特定財産額は増加します。
⑵ 控除対象財産の減少
控除対象財産を構成する財産が処分等により流動資産に置き換わった場合、使途不特定財産額が増加します。公益目的保有財産(認定規則36条3項1号)や法人活動保有財産(同2号)を売却して資金を得た場合、あるいは、公益充実資金(同3号)、資産取得資金(同4号)、特定費用準備資金(同5号)の目的外取崩しを行った場合等が該当します。
なお、目的取崩しの場合は、費用として純資産額を減少させるか、別の控除対象財産(公益目的保有財産等)に置き換わるため、使途不特定財産額への影響はありません。
⑶ 公益目的事業費の減少
公益目的事業費の減少は、純資産額の増加により当該年度の使途不特定財産額の増加をもたらします。一方、保有上限額への影響は、新制度では、原則として過去5年間平均の公益目的事業費の算定を通じて、翌年度以降5年間の減少をもたらすため、単年度の影響は従前より、緩和されることになります。
3 保有上限額超過の対応策
使途不特定財産の保有上限額超過に対しては、純資産額の減少または控除対象財産の額の増加をもたらす対策、あるいは保有上限額の算定基準となる公益目的事業費の額を増加させる対策が必要となります。なお、新制度では、保有上限額は、原則として過去5年間の公益目的事業費の平均で算定されるため、増加額は、翌年度以降5年均等で上限額に上乗せされることになります。
⑴ 公益充実資金の積立
公益充実資金(認定規則23条)は、旧制度の公益目的事業に係る「特定費用準備資金」及び「資産取得資金」を包括した資金とされ、事業を横断した設定も可能となります。積立額は、控除対象財産の額を増加させ、このうち費用への充当予定額は、翌年度以降5年間の保有上限額の拡大に寄与します。
公益充実資金の設定にあたっては、活動内容や実施時期、積立限度額や算定根拠等を記載した書類を作成し、備置き、行政庁に提出するとともに法人自らもインターネットの利用等により公表する必要があります。
⑵ 財産の取得又は改良、資金の積立
公益目的保有財産(認定規則36条3項1号)や法人活動保有財産(同2号)の取得又は改良は、控除対象財産を増加させます。
新制度では、公益充実資金が設定されたことにより、特定費用準備資金(同5号)は、公益目的事業以外の特定の活動実施のため支出する費用に充当される資金とされ、資産取得資金(同4号)は、法人活動保有財産の取得または改良に充当される資金とされます。いずれも積立は、控除対象財産の増加として、使途不特定財産額の減少をもたらします。
なお、特定費用準備資金及び資産取得資金の設定にあたっての積立要件(設定期間、実施時期の変更、目的外取崩し手続の定め等)については旧制度と同様となります。
⑶ 公益目的事業継続予備財産の積立
公益目的事業継続予備財産の積立は、控除対象財産と同様の効果があります。なお、保有にあたっては、予備財産の額や保有理由等について毎事業年度終了後、インターネットその他適切な方法で公表する必要があります。
⑷ 事業費・管理費の増加
事業費・管理費の増加は、純資産の額の減少をもたらします。このうち、公益目的事業費の増加は、前述の通り、新制度では翌年度以降5年間の保有上限額の拡大に寄与します。
4 財務諸表における開示
新公益法人会計基準における財務諸表では、控除対象財産は、貸借対照表の注記で、「使途拘束財産」としてその内訳と増減額及び残高を記載するとともに「資産及び負債の状況」(旧会計基準の財産目録に相当)の「使用目的等」欄にそれぞれ明示します。また、旧制度の定期提出書類別表C⑵に相当する情報は、附属明細書へ記載されます。
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら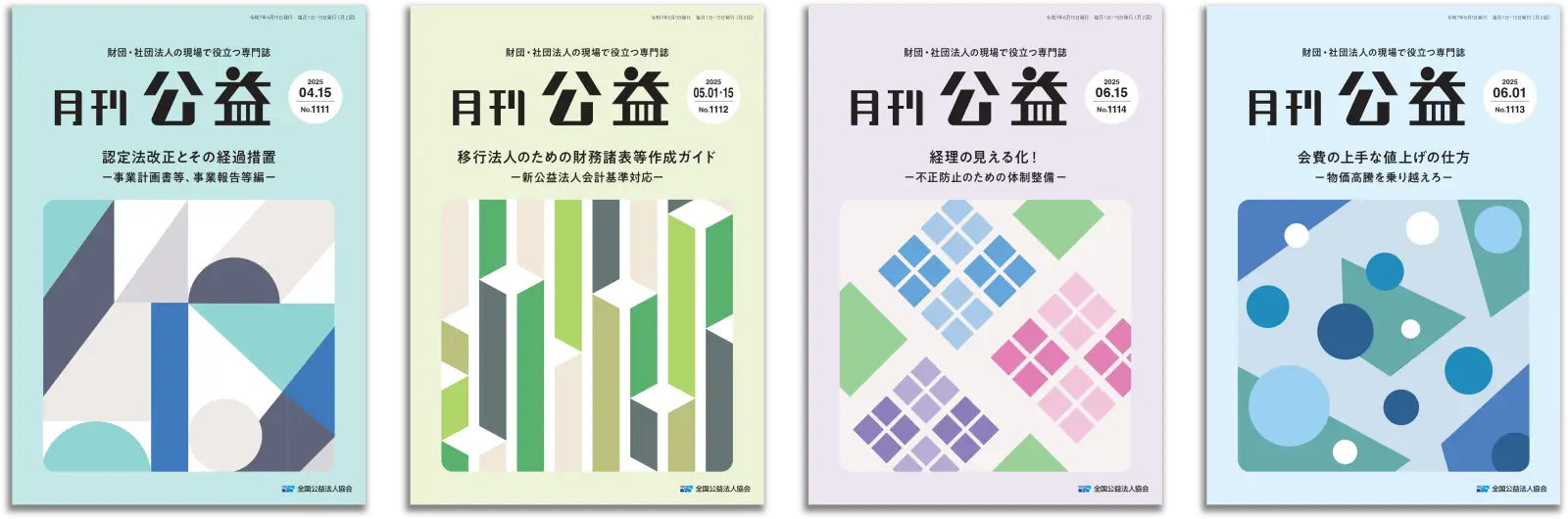
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
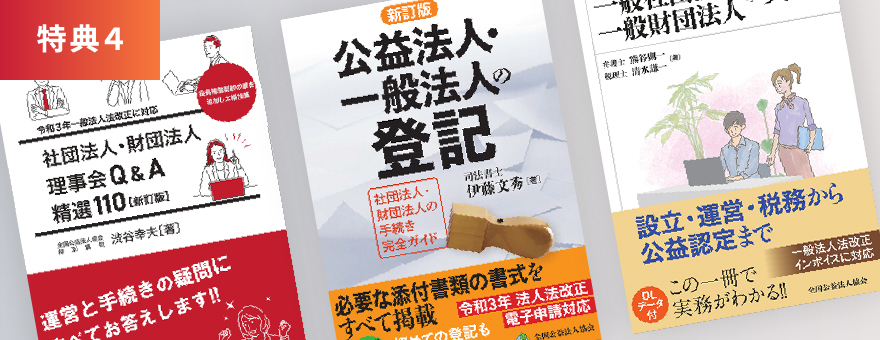
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。