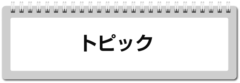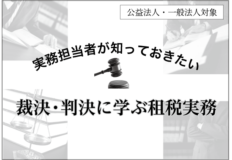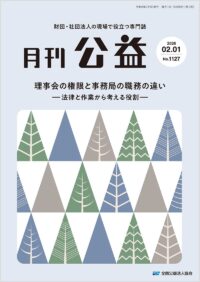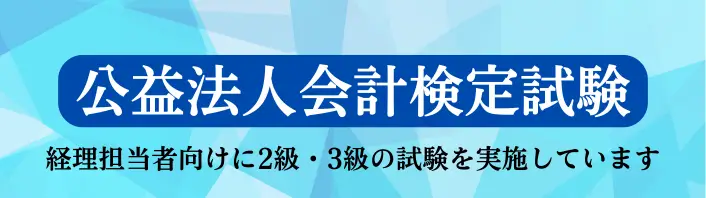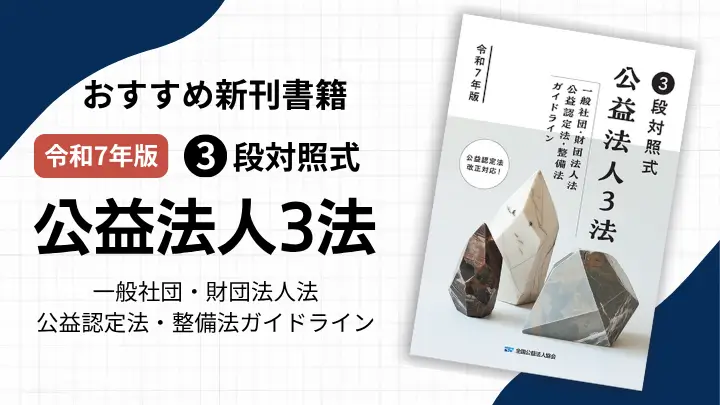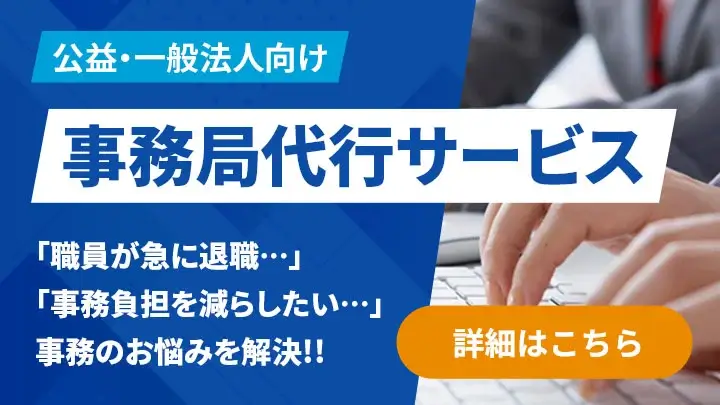公益法人会計と財務規律の行方

(ふじい・まこと 法政大学経営学部教授・(公社)非営利法人研究学会理事)
公益法人制度改革の一環として、財務規律の柔軟化・明確化を謳い、収支相償原則は中期的収支均衡へと改正された。我が国において、何かしらの規制を行う場合、当初は厳しい内容とし、その厳しさが被規制側の活動の制約となることが指摘されるようになると、規制を緩めるということが往々にして行われる。これは、文化や慣習、あるいは、国民性に起因するのかもしれないが、成文法系の制度を採っていることによるのかもしれない。
会計学的観点から興味深いのは、収支相償も中期的収支均衡も、収支に着目しているという点である。会計学におけるフロー概念には収支と損益の2 つがあるが、公益法人の財務規律においては、損益よりも収支が重視されている。一方、今般の改革に伴い、公益法人会計基準も改正され、従前の正味財産増減計算書は活動計算書へと名称変更され、その中身も大きく変化した。その結果、わかりやすさの向上を目的として、企業会計の損益計算書により接近したものとなった。このことは、公益法人の財務規律や会計情報における矛盾点が顕在化したものと見ることができる。
収支相償とは、公益目的事業に係る「収入」が適正な「費用」を超えないと見込まれることを求める改正前認定法5条6号と、公益法人はその公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な「費用」を償う額を超える「収入」を得てはならないと定める同14条を内容とする。これらの規定からも、文言上、損益と収支が混在していることが見て取れるが、それ以上に気になるのは、収入(収益)と費用(支出)のいずれが先なのかという疑問である。この疑問は、財政学における量出制入(出を量って入を制する)の考え方に通底する。ここで考えるべきは、入と出のいずれが先かということである。国や地方自治体のようなパブリックセクターは、出が先に量られて入を制するため、そこには税が不可避となる。一方、公益法人などのプライベートセクターは、どうであろうか。
期間の長短を除けば、収支相償と収支均衡は大きく意味が異なる。収支相償とは、支出が先で収入が後ということが含意された用語である。しかし、収支均衡という用語からは、獲得した収入の範囲内で身の丈に合った活動をすることを求めるとも解されうるため、収支の前後関係は曖昧になる。
かくして、公益法人を取り巻く会計の現状は、収支と損益のいずれが重視されるのかという問題に加え、入出のいずれが重視されるのかという疑問を我々に投げかけている。
法政大学経営学部教授・(公社)非営利法人研究学会理事
博士(経営学)。税務会計研究学会理事。専門は税務会計論、非営利組織会計論。青山学院大学大学院経営学研究科博士後期課程標準年限修了、横浜国立大学大学院国際社会科学府博士課程後期修了。日本大学商学部専任講師、同准教授、同教授を経て現職。著書に『デジタル社会の会計と法人課税』(編著、中央経済社)、他論文等多数。
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら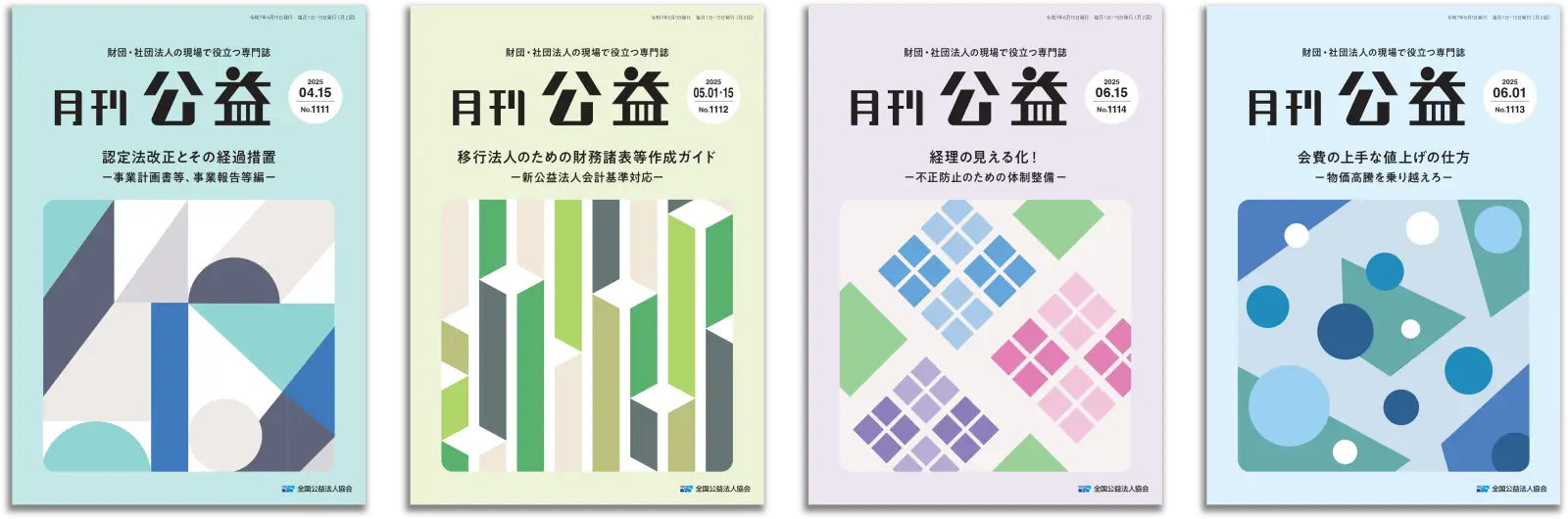
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
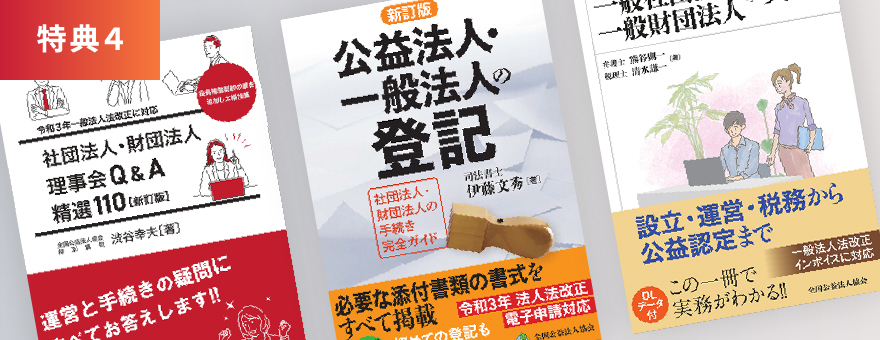
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。