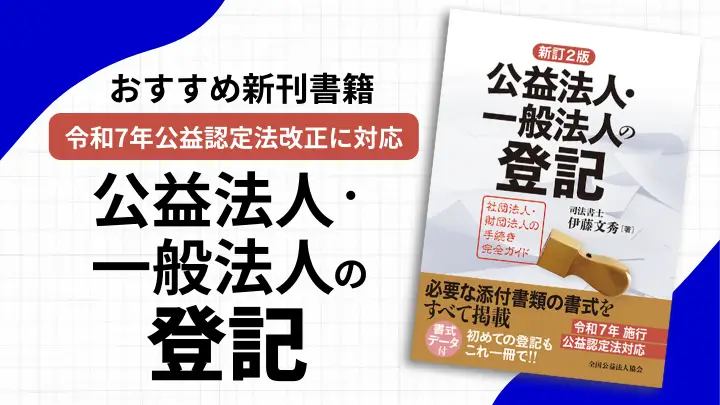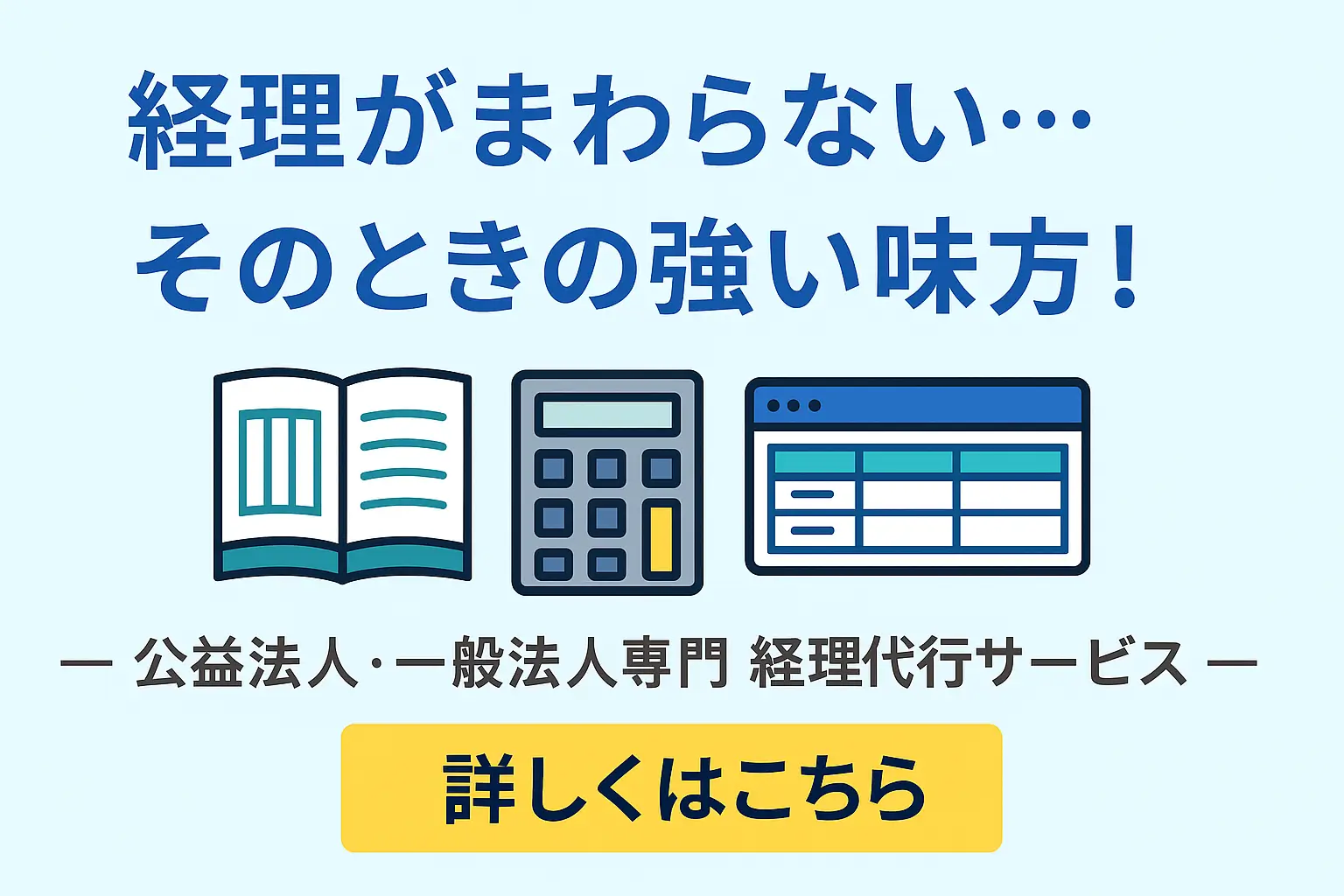収支予算書及びキャッシュ・フロー計算書を巡る一考察
2021年05月18日

源田佳史
(げんだ・よしふみ 公認会計士・税理士)
(げんだ・よしふみ 公認会計士・税理士)
- CATEGORY
- 会計処理
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
平成20 年基準が適用された後においても資金収支ベースの収支予算書を作成する法人は少なくない。新制度下におけるあるべき予算管理について考察する。
Ⅰ 収支予算書を巡る混乱
新制度への移行期間終了から2年近く経過しているにもかかわらず、従前の予算主義に基づく考え方(資金収支予算書の活用)が未だに公益法人あるいは一般法人の管理運営において、残っていることが、筆者が関係している法人でも見受けられる。この理由としては、以前の主務官庁による指導監督のための平成16年改正会計基準(以下「16年基準」という。)と、法人の自主的な管理に基づき外部に対して情報開示するための平成20年会計基準(以下「20年基準」という。)を十分に理解されていない可能性が挙げられる。また、法律上では、予算は法人の最高意思決定機関である社員総会や評議員会による決議ではなく、業務執行機関である理事会による決定、すなわち法人管理のためのガバナンスに関わる事項であるということが十分に理解されていないということが挙げられる。
法律にいうところの損益計算書ベースの予算書では、投資活動支出や財務活動に関わる予算が表示できないことを理由として、理事会等での参考資料として旧来の資金収支ベースでの予算書を作成しているケースも見受けられる。
このような混乱は何が原因であるか、本稿で考察する。
Ⅱ 資金の範囲による表示の違い
旧来の収支予算書並びに収支計算書は、ある意味、その定義にかなりの差があった「資金」という概念に基づくものであった。資金のうち、かなり狭義な現金預金を資金の範囲とする場合であっても、預金の期間ということでは短期(1年以内)の預金を資金の範囲とするという意味では不徹底なものであったといえ月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。

公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。