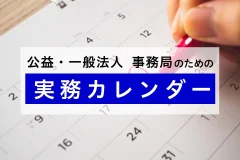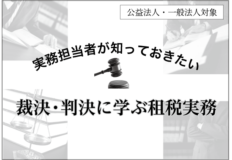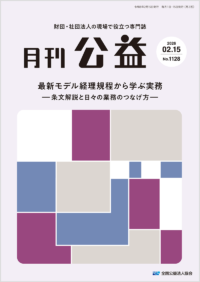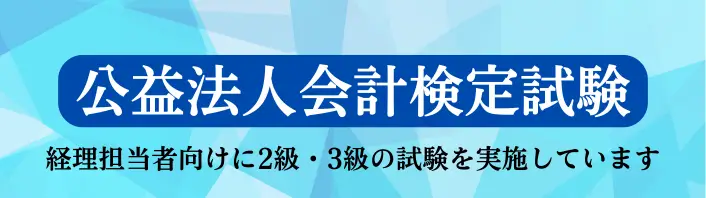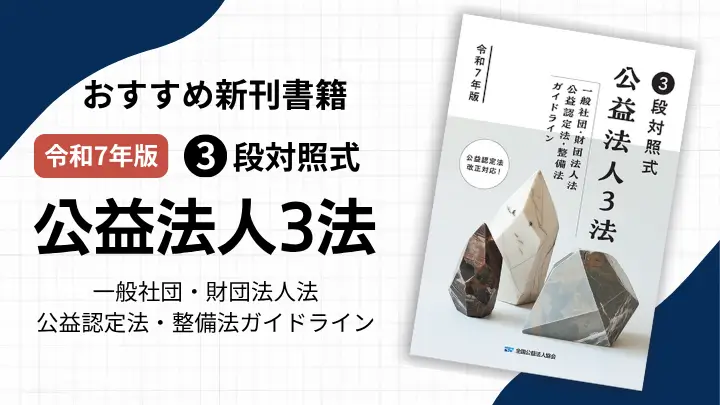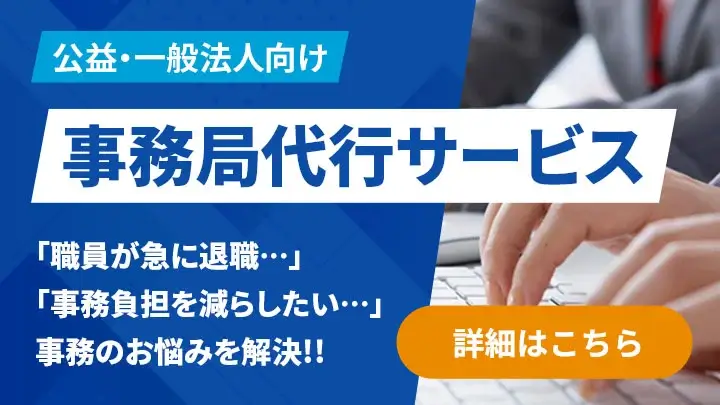理事会運営の基礎知識と進行シナリオの作成
2019年01月21日

理事会の途中で勝手に中座する理事、議案にないことを喋り出す理事など、理事会運営においてお困りの職員も多いのではないだろうか――。
本稿においてはまず、理事会の運営についての基本的なルールや、理事会の決議が無効となるのがどういう場合なのかについて確認する。次に、理事会を円滑に運営していくに当たって、法人が留意すべき点を幾つか挙げる。そして、最後に、理事会の進行シナリオを参考例として示すこととする。
理事会は、理事の全員で組織される会議体なので(法第90条第1 項)、理事が理事会に出席できることは当然である。
●理事の代理人
理事本人が代理人を選任して、その代理人に理事会に出席してもらうことはできるだろうか。
これについて、理事は、その個人的な能力や資質に着目し、法人運営を委任されているので(法第64条、第172条第1 項、民法第644条)、自ら理事会に出席し、議決権を行使することが求められており、理事の代理人による理事会への出席は認められないと解されている。
●監事
監事は、理事会に出席しなければならない。また、監事は、理事会に出席するだけでなく、必要があると認めるときは理事会で意見を述べなければならないとされている(法第101条第1 項、第197条)。
●理事会の決議により出席が認められる者
理事会がその決議により、必要に応じて、理事以外の者の理事会への出席を認めることもできると解される。理事会規則等において、「理事会は、理事及び理事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる」等と定めることも考えられる。
実務では、法人の事務局が理事会議事録の草案作成等のために出席したり、理事ではない法人の職員がその職務との関連において理事会に出席することもあると思われるが、これは、原則として、議長又は理事の補助者として理事会に関与していると考えられる。
これらの法人の職員は、その都度理事会の決議を経ることなく理事会に出席していることも多いと思われるが、これは、議長ないし理事会の黙示の同意により理事会に出席しているものと考えられる。
●特別利害関係を有する理事の出席の可否
決議について特別の利害関係を有する理事は、当該決議に関して、議決権を行使することはできないことは明らかであるが(法第95条第2 項)、当該議題の審議にも参加することができないのだろうか。
これについては、特別利害関係を有する理事は、当該決議については意見陳述権がなく、議長である場合にはその権限を失うと考えられており(東京地判平成7 年9 月20日判時1572号131頁等参照)、原則として、当該議題の審議にも参加できない。
もっとも、理事会において、当該理事に意見等を述べさせることが適当であると判断されるときには、理事会の決議により、当該理事の意見又は説明を聴くことが許容され、その限りで特別利害関係を有する理事の出席が許されるものと解される。
社員総会については、議長の権限について、「社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する」、「社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる」との定めがあるが(法第54条第1 項及び第2 項)、理事会の議長については、一般法人法に明文の規定が置かれていない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(以下、「施行規則」という。)第15条第3 項第8 号が、「理事会の議長が存するときは、議長の氏名」を理事会議事録に記載するよう定めているとおり、施行規則は、理事会において、議長が選任されていない場合があることを前提にしている。
理事会の議長を選任することは決議を成立させるための要件ではなく、議長不存在の下で決議がなされても、当該決議は有効である。しかし、実務上、円滑に議事を進行するために議長が置かれることが一般的である。
●議長の選任方法
実務上一般に、定款又は理事会規則等によって、代表理事が議長となる旨を定め、代表理事に事故があったときに備えて他の理事の代行順位を定めていることが多いと思われる。
理事全員が改選期である場合には、理事を選任する社員総会又は評議員会の直後に開催される理事会において、理事の互選により議長を選出することが一般的であろう。
議長の資格についてとくに規定はないが、理事会は、社員総会又は評議員会において選任された理事の会議であるため、議長となり得る者は理事に限られると解される。
定款や理事会規則等に議長の定めがあっても、理事会は、当該理事会限りの議長を選任することができる(福岡地判平成5 年9 月30日判時1503号142頁参照)。
●特別利害関係を有する理事が議長になることの可否
決議について特別の利害関係を有する理事は、議長になることはできないと考えられている(前掲東京地判平成7 年9 月20日等参照)。
●議長の権限
議長は、理事会開催に当たって定足数を満たしていることを確認し、開会を宣言して議事を進行する。議題に関する審議が十分に行われたと判断されるときは、決議が必要である場合には採決をとり、閉会を宣言する。
理事会の議長については、社員総会の議長の権限に関する一般法人法第54条のような明文の規定は置かれていない。具体的な理事会の運営方法について、定款又は理事会の定めがあるときは、それに従うことになるが、特別の定めがないときは、会議運営の一般原則に従って、合理的に運営されることになる。
●議長の議事進行に関する権限
理事会の議長については、社員総会の議長と異なり、法律上、秩序維持権、議事整理権及び退場命令権が規定されていないが(一般法人法54条参照)、理事会の議長も、会議体の主催者として会議の秩序を維持し、議事を整理する機能を本質的に持っており、議事を公正かつ円滑に進行するために必要な権限が認められるべきであると解される。
ただ、個々の理事は、他の理事の職務執行を監督する立場にあるため、特定の理事が理事会の議事進行を乱すからといって、簡単に理事会への出席の機会を奪われるべきではない。理事を理事会から退場させる場合には、不公正な議事運営にならないよう慎重に対応すべきである。
議長が特定の理事に退室を命じる場合には、原則として、理事会の意見を仰いで退室を命じるべきである。
●議長の決裁権
「可否同数のときは、議長の決するところによる」旨の定款規定が有効であるか否か、という問題があるが、これについては、後述する。
実務上一般に、議長が開催に当たって定足数を満たしていることを確認し、開会を宣言することにより、理事会は開催される。この開会宣言は、招集手続や出席者数等の確認の手続が適法に行われたことを確認し、会議の開始を出席者に認識させるものである。もっとも理事会の開会には、必ずしも議長の宣言が必要であるわけではなく、適宜な方式により、理事会という会議が開始されることが、会議体の出席者に認識され得る方法で行われればよいと考えられる。
●理事会の閉会
実務上一般に、議長による閉会の宣言をもって理事会が閉会とされるが、理事会の閉会には、議長による閉会の宣言が不可欠のものではなく、適宜な方式により、理事会が終了したということが理事等に認識され得る方法で行われればよいと考えられる。
理事会における理事の議決権は、1人1票である。特別利害関係を有する理事は、議決に加わることができ
吉田宏喜
(よしだ・ひろき 弁護士)
(よしだ・ひろき 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営、理事会、司会進行
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- 理事会の運営についての基本的なルール
- ・理事会の出席者
- ・理事会の議長
- ・理事会の開会と閉会
- ・理事会の決議(決議要件)
- ・理事会の議題
- 理事会の決議が無効となる場合
- 理事会を円滑に運営していくに当たって、法人が留意すべき点
- 理事会当日のシナリオの参考例
- おわりに
はじめに
理事会については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」又は「法」という。)第90条から第98条に規定が置かれている。しかし、理事会の運営について定める規定が少ないこともあり、その運営について、悩んでいる法人も多いのではないかと思われる。そこで、本稿では、理事会を円滑に運営するために押さえておくべき事項について解説する。本稿においてはまず、理事会の運営についての基本的なルールや、理事会の決議が無効となるのがどういう場合なのかについて確認する。次に、理事会を円滑に運営していくに当たって、法人が留意すべき点を幾つか挙げる。そして、最後に、理事会の進行シナリオを参考例として示すこととする。
理事会の運営についての基本的なルール
それでは、理事会の運営についての基本的なルールとして、①理事会の出席者、②理事会の議長、③理事会の開会と閉会、④理事会の決議(決議要件)、⑤理事会の議題の5 つのテーマについて確認しよう。理事会の出席者としてふさわしい者は?
●理事理事会は、理事の全員で組織される会議体なので(法第90条第1 項)、理事が理事会に出席できることは当然である。
●理事の代理人
理事本人が代理人を選任して、その代理人に理事会に出席してもらうことはできるだろうか。
これについて、理事は、その個人的な能力や資質に着目し、法人運営を委任されているので(法第64条、第172条第1 項、民法第644条)、自ら理事会に出席し、議決権を行使することが求められており、理事の代理人による理事会への出席は認められないと解されている。
●監事
監事は、理事会に出席しなければならない。また、監事は、理事会に出席するだけでなく、必要があると認めるときは理事会で意見を述べなければならないとされている(法第101条第1 項、第197条)。
●理事会の決議により出席が認められる者
理事会がその決議により、必要に応じて、理事以外の者の理事会への出席を認めることもできると解される。理事会規則等において、「理事会は、理事及び理事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる」等と定めることも考えられる。
実務では、法人の事務局が理事会議事録の草案作成等のために出席したり、理事ではない法人の職員がその職務との関連において理事会に出席することもあると思われるが、これは、原則として、議長又は理事の補助者として理事会に関与していると考えられる。
これらの法人の職員は、その都度理事会の決議を経ることなく理事会に出席していることも多いと思われるが、これは、議長ないし理事会の黙示の同意により理事会に出席しているものと考えられる。
●特別利害関係を有する理事の出席の可否
決議について特別の利害関係を有する理事は、当該決議に関して、議決権を行使することはできないことは明らかであるが(法第95条第2 項)、当該議題の審議にも参加することができないのだろうか。
これについては、特別利害関係を有する理事は、当該決議については意見陳述権がなく、議長である場合にはその権限を失うと考えられており(東京地判平成7 年9 月20日判時1572号131頁等参照)、原則として、当該議題の審議にも参加できない。
もっとも、理事会において、当該理事に意見等を述べさせることが適当であると判断されるときには、理事会の決議により、当該理事の意見又は説明を聴くことが許容され、その限りで特別利害関係を有する理事の出席が許されるものと解される。
理事会の議長って誰がして何ができるの?
●議長の選任社員総会については、議長の権限について、「社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する」、「社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる」との定めがあるが(法第54条第1 項及び第2 項)、理事会の議長については、一般法人法に明文の規定が置かれていない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(以下、「施行規則」という。)第15条第3 項第8 号が、「理事会の議長が存するときは、議長の氏名」を理事会議事録に記載するよう定めているとおり、施行規則は、理事会において、議長が選任されていない場合があることを前提にしている。
理事会の議長を選任することは決議を成立させるための要件ではなく、議長不存在の下で決議がなされても、当該決議は有効である。しかし、実務上、円滑に議事を進行するために議長が置かれることが一般的である。
●議長の選任方法
実務上一般に、定款又は理事会規則等によって、代表理事が議長となる旨を定め、代表理事に事故があったときに備えて他の理事の代行順位を定めていることが多いと思われる。
理事全員が改選期である場合には、理事を選任する社員総会又は評議員会の直後に開催される理事会において、理事の互選により議長を選出することが一般的であろう。
議長の資格についてとくに規定はないが、理事会は、社員総会又は評議員会において選任された理事の会議であるため、議長となり得る者は理事に限られると解される。
定款や理事会規則等に議長の定めがあっても、理事会は、当該理事会限りの議長を選任することができる(福岡地判平成5 年9 月30日判時1503号142頁参照)。
●特別利害関係を有する理事が議長になることの可否
決議について特別の利害関係を有する理事は、議長になることはできないと考えられている(前掲東京地判平成7 年9 月20日等参照)。
●議長の権限
議長は、理事会開催に当たって定足数を満たしていることを確認し、開会を宣言して議事を進行する。議題に関する審議が十分に行われたと判断されるときは、決議が必要である場合には採決をとり、閉会を宣言する。
理事会の議長については、社員総会の議長の権限に関する一般法人法第54条のような明文の規定は置かれていない。具体的な理事会の運営方法について、定款又は理事会の定めがあるときは、それに従うことになるが、特別の定めがないときは、会議運営の一般原則に従って、合理的に運営されることになる。
●議長の議事進行に関する権限
理事会の議長については、社員総会の議長と異なり、法律上、秩序維持権、議事整理権及び退場命令権が規定されていないが(一般法人法54条参照)、理事会の議長も、会議体の主催者として会議の秩序を維持し、議事を整理する機能を本質的に持っており、議事を公正かつ円滑に進行するために必要な権限が認められるべきであると解される。
ただ、個々の理事は、他の理事の職務執行を監督する立場にあるため、特定の理事が理事会の議事進行を乱すからといって、簡単に理事会への出席の機会を奪われるべきではない。理事を理事会から退場させる場合には、不公正な議事運営にならないよう慎重に対応すべきである。
議長が特定の理事に退室を命じる場合には、原則として、理事会の意見を仰いで退室を命じるべきである。
●議長の決裁権
「可否同数のときは、議長の決するところによる」旨の定款規定が有効であるか否か、という問題があるが、これについては、後述する。
理事会の開会と閉会宣言は必要?
●理事会の開会実務上一般に、議長が開催に当たって定足数を満たしていることを確認し、開会を宣言することにより、理事会は開催される。この開会宣言は、招集手続や出席者数等の確認の手続が適法に行われたことを確認し、会議の開始を出席者に認識させるものである。もっとも理事会の開会には、必ずしも議長の宣言が必要であるわけではなく、適宜な方式により、理事会という会議が開始されることが、会議体の出席者に認識され得る方法で行われればよいと考えられる。
●理事会の閉会
実務上一般に、議長による閉会の宣言をもって理事会が閉会とされるが、理事会の閉会には、議長による閉会の宣言が不可欠のものではなく、適宜な方式により、理事会が終了したということが理事等に認識され得る方法で行われればよいと考えられる。
理事会の決議(決議要件)をおさらい
●議決権理事会における理事の議決権は、1人1票である。特別利害関係を有する理事は、議決に加わることができ
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら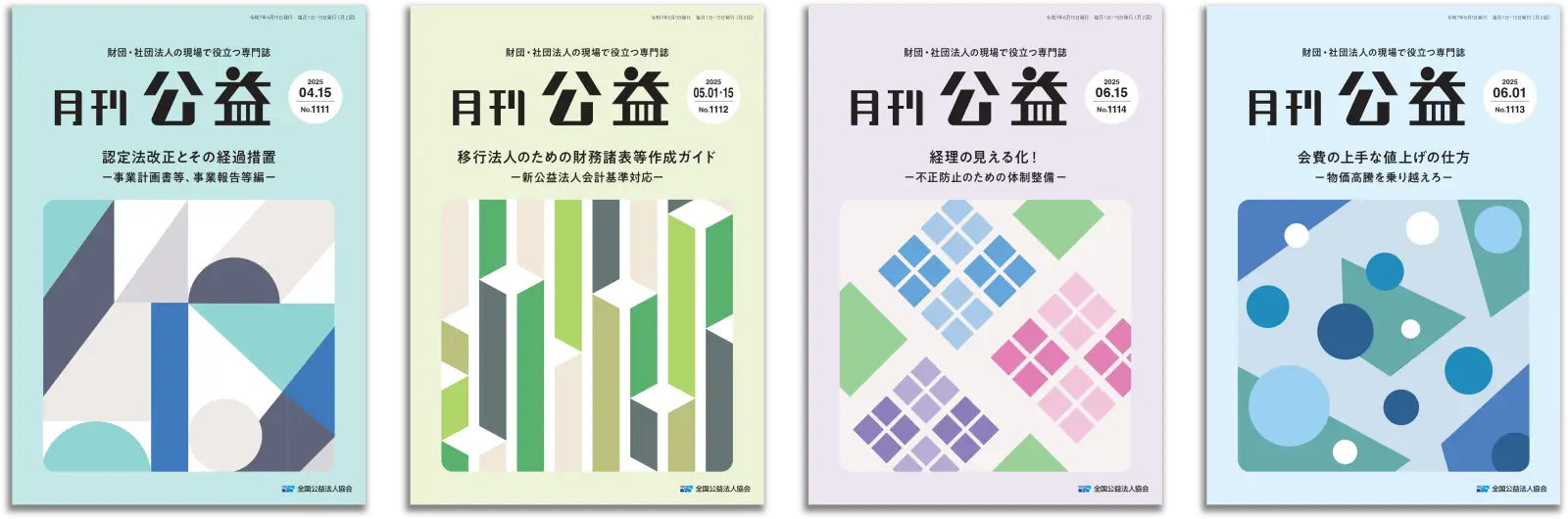
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
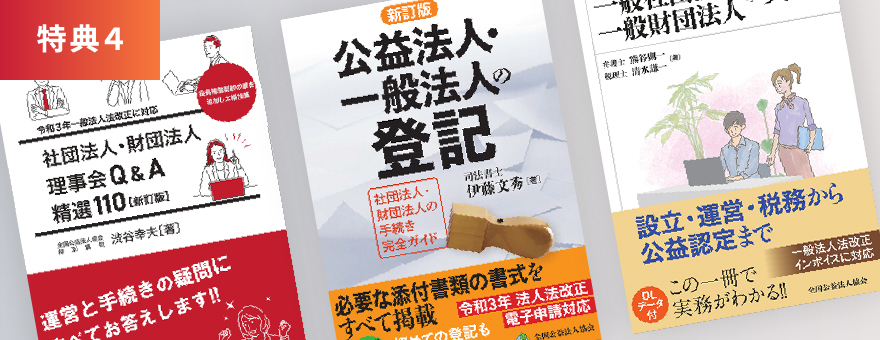
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。