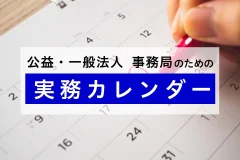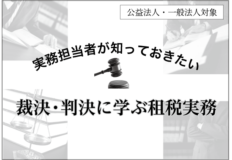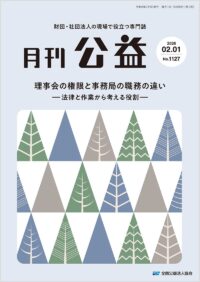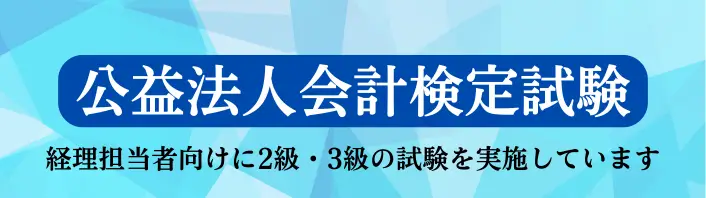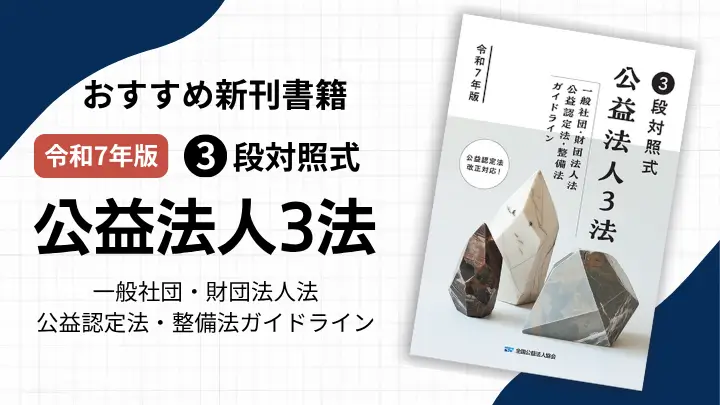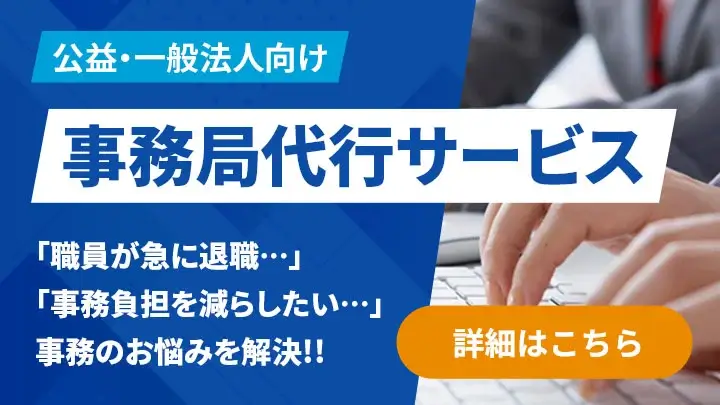理事の定年制導入に向けた具体的方法と留意点
2019年04月19日

渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
我が国では現在、約4人に1人が65歳以上であり、令和7(2025)年には65歳以上が3人に1人、75歳以上が人口に占める割合は18%となるようである。人手不足の昨今だが、組織のガバナンス上、年齢で一定の線引きを求める声も少なくない。
Ⅰ 理事の任期と定年制
1 理事の在任期間の長期化
理事の任期について、一般法人法66条(法177条)は「理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会・定時評議会の終結の時までとする。ただし、定款<又は社員総会の決議>によって、その任期を短縮することを妨げない」と規定している。一般社団・財団法人、公益法人の理事の任期満了に伴う後任理事の選任に際しては、法人によっては、再任の反復により在任期間が長期化し、また理事の年齢も高齢化の傾向にある。
在任期間の長期化の理由としては、以下のもの等が挙げられる。
理事の在任期間長期化の理由㋐ 法人の運営手腕・専門知識への評価㋑ 担当職務の安定的継続㋒ 後任適任者の確保が困難㋓ 当該理事の功績への配慮㋔ 派閥上の均衡人事㋕ 該当者に対する退任勧告への心理的抵抗感また理事の在任期間の長期化の得失を挙げると以下のとおり等である。
理事の在任期間長期化のメリット㋐ 一貫性のある法人運営㋑ 優れた人材の確保㋒ 選任事務の負担、手数の節減理事の在任期間長期化のデメリット㋐ 特定理事との利害関係の深化㋑ 特定理事による独断専行的法人運営㋒ 理事の欠席恒常化による理事会の会議体機能の減退・喪失㋓ 人事のマンネリ化による運営活性化への阻害
2 在任長期化への対応策と定年制
理事の在任期間の長期化についての短所が顕在化し、理事の長期在任や高齢化を抑制する必要が生じた場合、その対応策としては、以下のもの等が考えられる。理事の長期在任・高齢化抑制対応策㋐ 理事の再任回数の制限㋑ 抜群の功績者に対する名誉的地位による処遇㋒ 理事の定年制の採用会社法下における取締役会の運営実績において、取締役の定年制について調査した結果(平成21年1月東京、大阪、名古屋等5証券取引所に上場されている国内会社2,532社にアンケート調査を実施した結果。商事法務№334)では、419社(回答会社全体の46.5%)が「定年制がある」と回答されている。
理事の定年制については、改正前民法法人(改正前民法34条に基づく公益法人)にあっても、各般において論じられてきた。しかし、現実に理事会においてこれを採り上げて議論するには、当該理事会の構成員の中には、既に設けようとする定年制設定基準を超えている理事が含まれていること等から、意見調整ができず、多くの場合これまで見送られてきたというのが実態である。この実態は、新しい法人制度に移行した現在においても、変わっていないと考えられる。
Ⅱ 理事の定年制導入の方法
理事の定年制を設けることについては、理事の高齢化に伴う法人運営の硬直化を防ぎ、若返りを図り、そして法人運営の活性月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら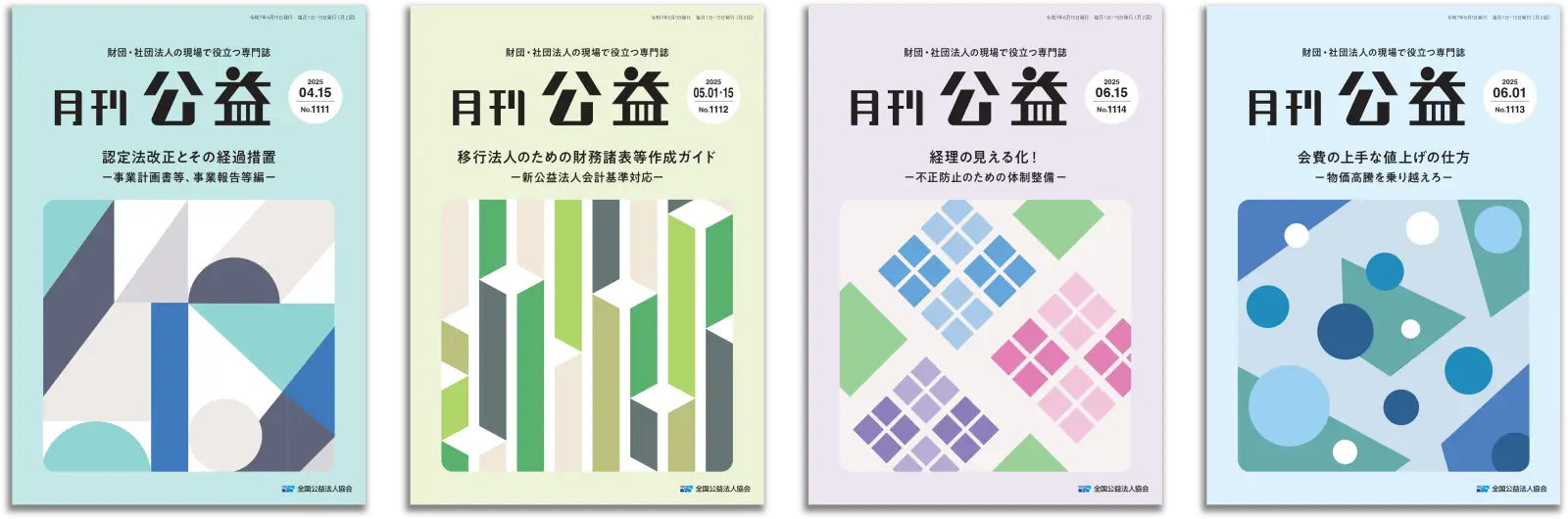
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
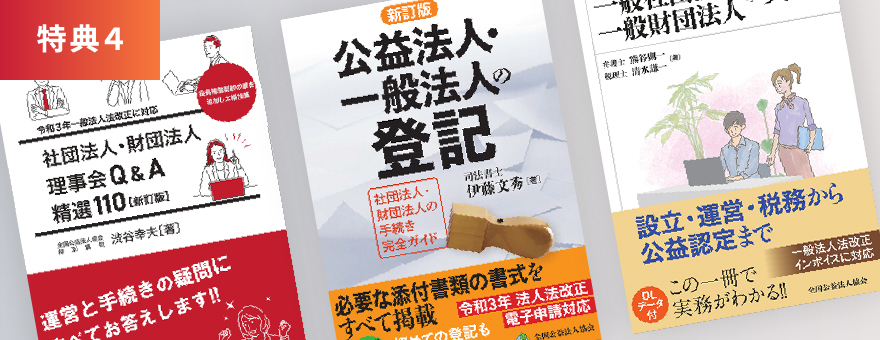
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。