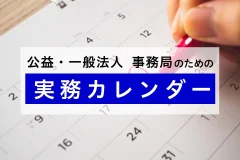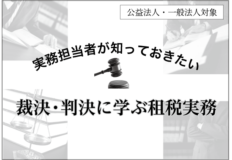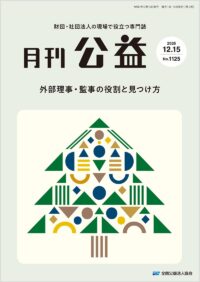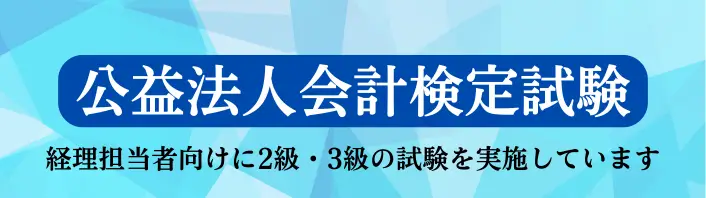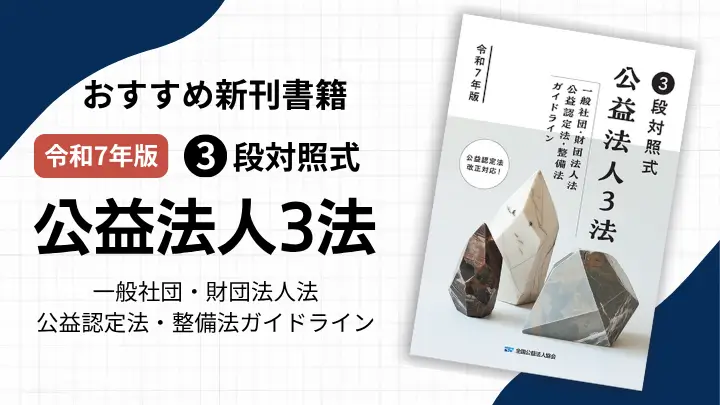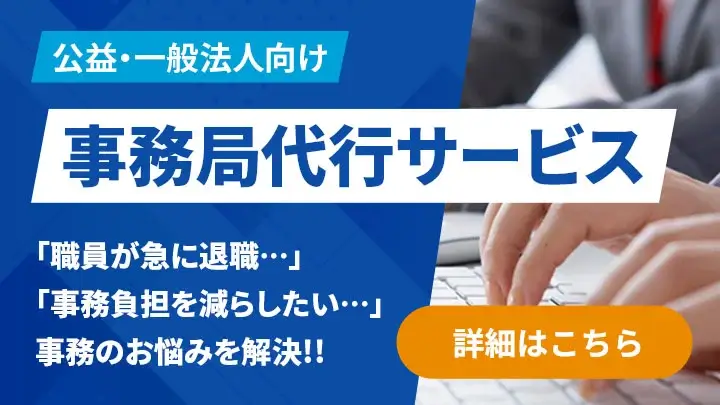公益目的事業の該当性チェック!
基準と確認事項を詳しく解説

(やました・ゆうじ 税理士)
1.公益目的事業とは?
⑴ 要件
公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する認定法別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいいます(認定法第2条第4号)。
つまり、要件として以下の2つが求められます。
①認定法別表各号に掲げる種類の事業であること
②不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであることが求められます。
⑵ 23種の事業区分
上記①の認定法別表各号に掲げられている事業は、その性質上何らかの形で不特定かつ多数の者に利益をもたらすと考えられます。国民の利益のために制定されている立法当時有効な法律の目的規定を抽出・集約し、列挙したものです。およそ公益と考えられる事業目的は、別表各号のいずれかに位置付けることができます。
具体的には下記のような事業が掲げられています。
【公益目的事業の23種の事業区分】
(認定法 別表(第2条関係))
2.公益目的事業に認定されるには?
⑴ 公益目的事業該当性の判断基準
下記①~⑥のすべてに該当する場合に公益目的事業に該当すると整理されます。公益認定の審査・監督に当たっては、原則として、公益目的事業として求められる趣旨等に応じて、重点的にチェックを行う必要がある事項のみ確認されます。
それ以外の事項については、法人の事業内容に照らして当該事情を確認すべき特段の事情がある場合を除いて、法人のガバナンスに委ねることになっています。
【公益目的事業該当性の判断基準】
(ガイドラインp23,24)
⑵ 公益目的事業該当性の確認方法
典型的な事業については、公益目的事業該当性を簡便に判断することができるよう、19事業区分ごとのチェックポイントを示しています。チェックポイントに示した事業区分は、多種多様な公益目的事業の一部に過ぎません。
チェックポイントにない事業については、事業の特性に応じて軽重を付け、重要事項に集中して公益性の確認が行われることになります。
【ガイドラインにチェックポイントが示されている19事業】
(ガイドラインp48-69)
3.公益目的事業該当性を判断するための具体的な確認事項
⑴ 事業の趣旨・目的
公益目的(認定法別表に掲げる目的)及び不特定多数の者の利益の増進が主たる目的として位置付けられており、適切な方法で明らかにされているかが確認されます。定款上の事業や目的が抽象的である場合などには、当該事業が定款上の事業や目的に根拠があるかの判断ができない可能性があります。定款には具体的に記載することが望ましいです。
⑵ 収益性の高い事業についての確認事項
① 公益目的事業に収益性が高い付随的事業が含まれている場合
事業計画等に記載された収益性の高い付随的事業が、幹となる事業の効果的な実施等に資することの合理性が疑われる場合には、追加的に説明を求めることがありえます。
この場合における付随的事業とは、幹となる事業の1割程度(単発の事業にあっては3割程度)を超えない事業となります。付随的事業を超える事業規模になると、独立した事業として捉えることになります。
収益性の高い事業を公益目的事業の一部として実施する場合は、次の要件を満たす必要があります。
② 営利企業等が行う事業と類似する事業を営む場合
なぜ公益法人が当該事業を実施する必要があるか、当該事業を通じてどのように社会に貢献しようとし、そのためにどのような態様で当該事業を実施しようとしているか等が問われます。
公益目的事業としての特徴がなく、営利企業等による類似事業の実施状況を勘案して、高い税制上の優遇措置を受けるなどの社会的なサポートを受けてまで公益法人が実施する意義が認められない場合には、公益目的事業として認められません。
⑶ 受益の機会の確認事項
不特定かつ多数の者に受益の機会が開かれているか、また、機会が限定される場合には、当該限定を行う合理性及び当該限定があっても利益が不特定多数の者に及ぶことについて合理的説明があるかが問われます。
⑷ 受益者の義務・受益の条件についての確認事項
受益者の義務・受益の条件は、申請書に記載された公益目的事業の趣旨・目的に照らして合理的なものであるかが問われます。当該義務により、営利企業等や法人関係者に、合理的な範囲を超える利益が生じると見込まれる場合には、公益目的事業としては認められません。
⑸ 事業の合目的性の確保についての確認事項
事業内容に応じた適正運営の確保、事業内容に応じた専門家の関与、訓練、機材の確保、事業の趣旨に応じたプロセス(ニーズ調査や関係者の参加)の確保など、事業の趣旨・目的を踏まえ、必要に応じて、事業の質や成果を確保する取組がなされているかが問われます。
4.公益目的事業に関するよくあるQ&A
税理士・行政書士。全国公益法人協会相談室顧問。税理士試験試験委員。平成18年に山下雄次税理士事務所を設立。著書に『チャットでわかる社団・財団の経理・総務の仕事』(全国公益法人協会)等。
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら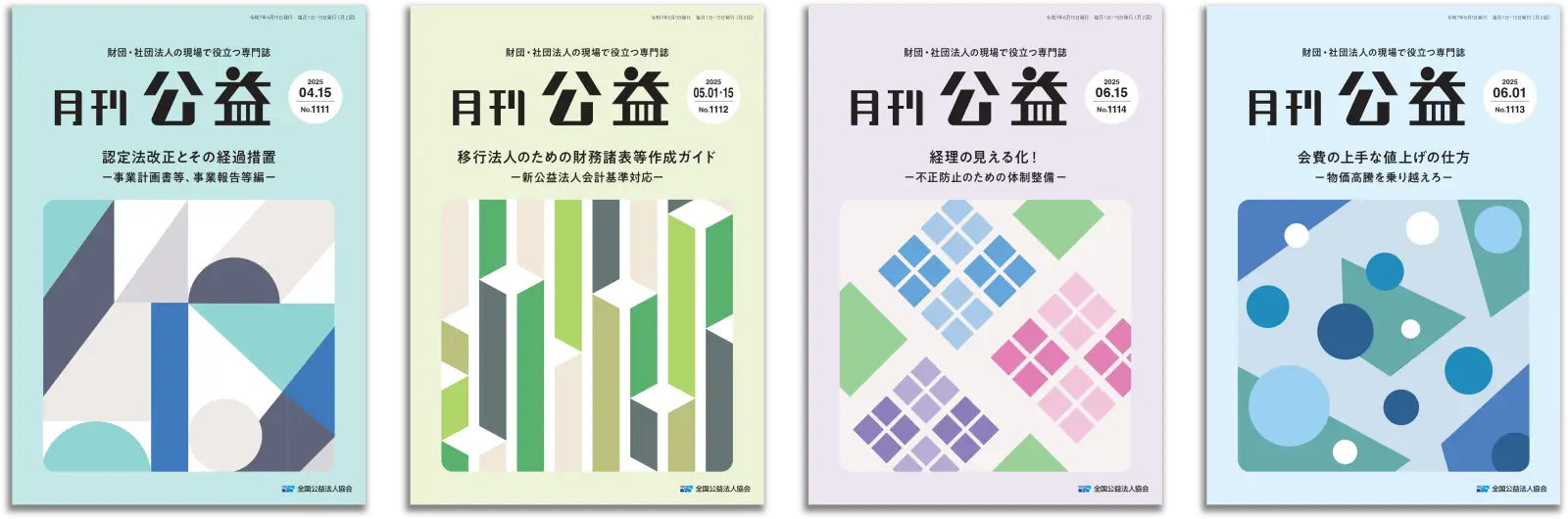
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
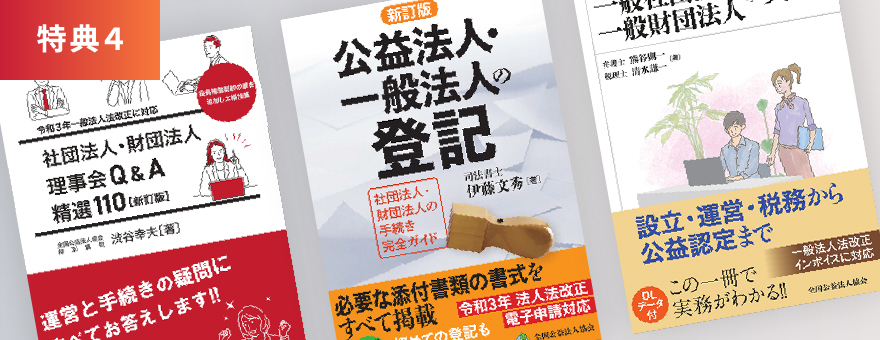
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。