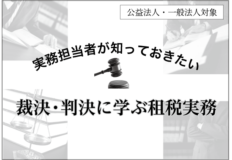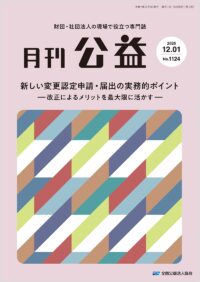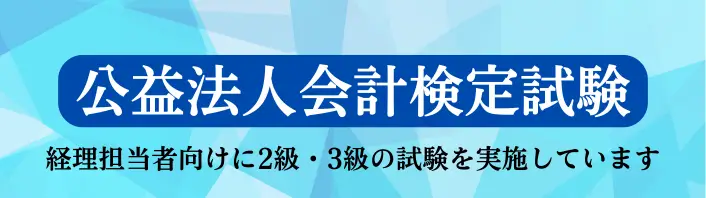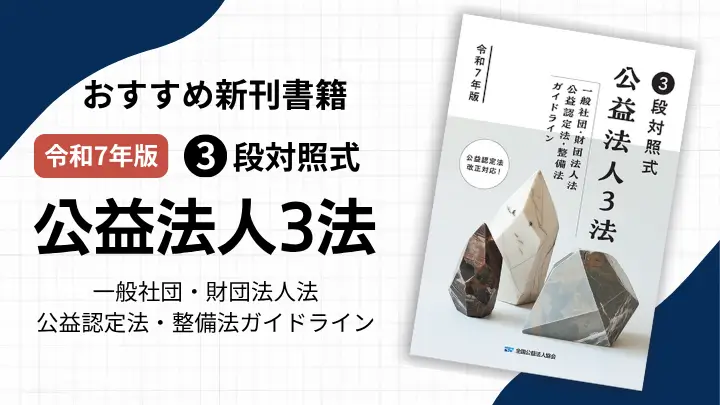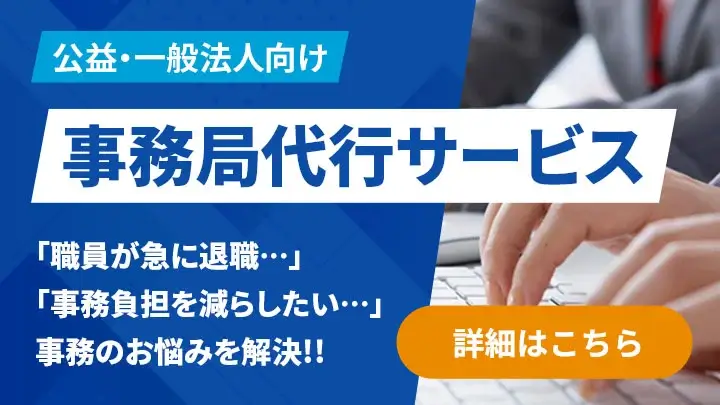公益法人の相談体制に“セカンドオピニオン”という選択肢を

(うえなか・たかあき 税理士)
法人の運営においては、経営、財務、労務など多岐にわたり判断が求められます。とりわけ公益法人では、公益法人特有の制約や説明責任が求められる局面が多く、意思決定には慎重さが求められます。そんなときに役立つのが「セカンドオピニオン」という選択肢です。
本稿では、公益法人におけるセカンドオピニオンの意義や具体的な活用場面、専門家の選び方までを実務的な視点で整理し、わかりやすく解説します。
1.セカンドオピニオンが求められる背景
セカンドオピニオンとは、主に医療の分野で主治医とは別の医師の意見を聞くことでよりよい判断を行うための行為、またはその意見のことをいいます。セカンドオピニオンは医療の分野に限らず、士業などの専門家にも用いられる概念です。
例えば、税務や法務などにおいて課題が生じた際、顧問税理士・弁護士などの専門家に相談することと思います。顧問契約しているため、普段から法人と接点があり法人特有の事情を理解しており、適切な助言を受けられることが見込まれます。しかし、特殊な事例など、法人が抱える課題によっては専門家により知見やアドバイスの内容が異なるケースが見受けられます。
そのような時に、セカンドオピニオンとしてほかの専門家に意見を求めることがあります。セカンドオピニオンは、当初の相談結果の確度を上げることや理解を深めるために利用するだけでなく、別の選択肢を得たい時や当初の相談結果に疑義がある時に第三者の意見を求める理由で利用することもあります。一般企業では、不正行為への対応など特殊な事態が発生した場面などでセカンドピニオンを活用する動きが広がっています。
2.公益法人での有用な活用場面
全国公益法人協会が公益法人と一般法人を対象に実施した「公益・一般法人 実態調査アンケート(令和6年10月18日)」によれば、調査に回答した法人の8割以上が税理士または公認会計士と顧問契約を結んでいます。特に、公益法人に限定すると、全ての法人が税理士または公認会計士と契約しているという結果でした。半分以下にとどまるものの、社会保険労務士や弁護士と顧問契約している法人も多くありました。公益法人も、営利企業と同様に、各分野の専門家と顧問契約を締結している法人が多くあることが見て取れます。
こうした法人は、法人運営上の課題が発生すると、まず顧問の専門家に頼ることが多いのではないでしょうか。特に、地元の税理士や社会保険労務士、弁護士などと顧問契約を締結している公益法人は、専門家が身近な相談相手となっているため、困ったことがあればすぐに相談する体制が自然とできていることと思われます。
地元の専門家は身近で相談しやすいというメリットがあります。しかしながら、専門家にも得意・不得意があるのが実情です。相談内容が特殊な事例である場合には、その専門家が相談分野に十分に精通していないということもあり得ます。特に公益法人の分野で経験が少ない場合には、相談分野に精通していないことにより最善のアドバイスを得られないことが想定されます。そのような時はセカンドオピニオンの活用が有効であると考えられます。
3.セカンドオピニオンを活用するメリットとその影響
例えば、財務上の問題から公益法人が保有している基本財産を取り崩して事業費の財源に充てたいと考えたとします。顧問税理士に相談すると、基本財産を取り崩す会計処理の指導を受けられたとしても、公益法人の分野に精通していないと全体として適切なアドバイスを受けられるとは限りません。そもそも基本財産を取り崩すことに問題がないかということや、基本財産を取り崩すための手順や手続きについて等、総合的なアドバイスが重要になるためです。
そのような時には公益法人に関する知見を持った専門家にセカンドオピニオンを求めることが有効です。適切な手続きを経ずに不適切な法人運営を行ってしまう事態を防ぐことが期待できます。
このように会計だけでなく、税務やガバナンスなどにおいて、公益法人特有の論点に適切に対応し、公益法人として適正な運営を行えるよう体制を整備しておくことが大切です。
4.活用のポイント
セカンドオピニオンを活用する際は、相談内容に応じて、適切な専門家へ依頼する必要があります。主な専門家の専門分野は以下のとおりです。
【相談先となる主な専門家の専門分野】
|
専門家
|
専門分野
|
|---|---|
| 弁護士 | 法律業務全般(裁判、交渉、示談、契約書作成など)など |
| 社会保険労務士 | 社会保険、労務など(社会保険手続きや就業規則作成など) |
| 司法書士 | 登記手続きなど(役員変更登記や不動産登記など) |
| 税理士 | 税務相談、税務申告書の作成など |
| 公認会計士 | 監査業務など |
| 行政書士 | 官公署に提出する書類(許認可申請等)に関する業務など |
| 弁理士 | 知的財産権(特許権、意匠権、商標権)に関する業務など |
税理士としか顧問契約をしていないため、どのような内容であっても顧問税理士に相談するというケースも見かけますが、専門分野以外については、適切な回答ができない(または、独占業務のため回答できない)こともあります。法人が抱える課題に対して適当な専門家へ相談することが重要です。特に、公益法人の分野は一般企業とは異なる論点もあるため、公益法人の分野で実績のある専門家へ依頼することがポイントになります。そうでなければ、せっかくセカンドピニオンを求めたとしても適切なアドバイスを受けられないことがあるためです。
5.まとめ
予算の都合や、結論を出すまでの時間的制約などにより、別の専門家の意見を求めることが難しいケースもあるかもしれませんが、法人運営においてセカンドオピニオンの活用も選択肢の一つにすると良いでしょう。
これまで、セカンドオピニオンを求めたことがなく、検討したこともないという法人であっても、普段とは異なった想定外の事態が発生した際には、セカンドオピニオンという方法もあると思い出していただければ幸いです。
税理士。全国公益法人協会相談室顧問。みずほインベスターズ証券(現みずほ証券)、財団法人、KPMG税理士法人等を経て税理士事務所を開設。公益法人への会計・税務・運営面の総合的な支援業務を中心に従事。
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら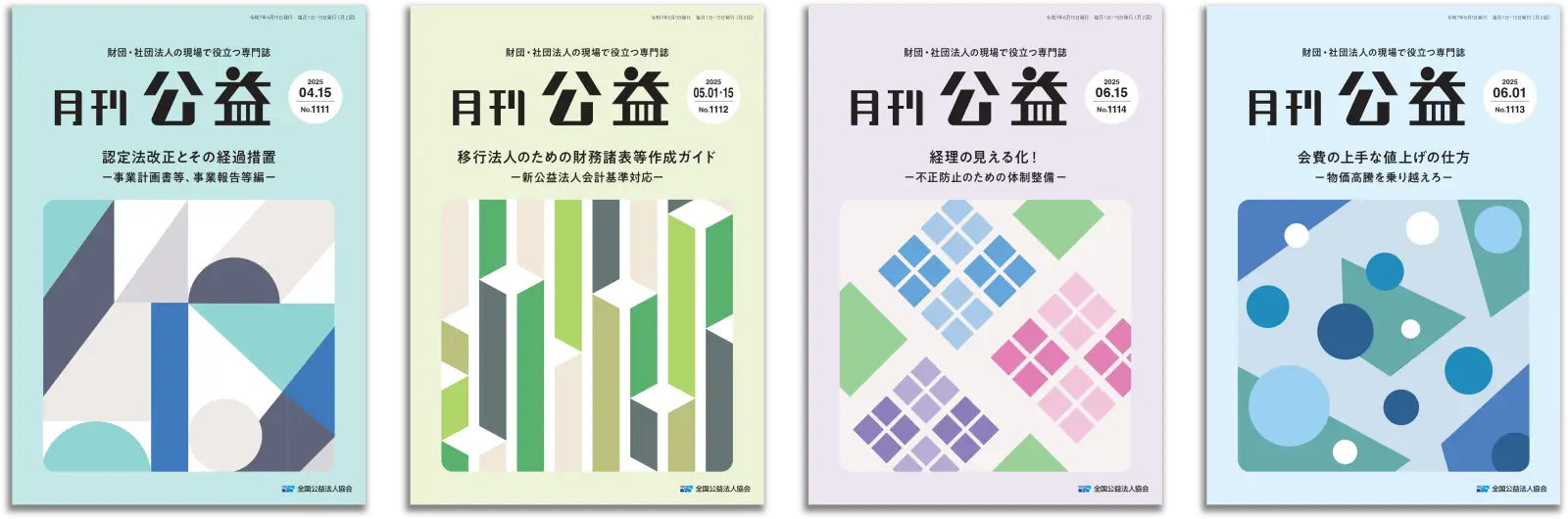
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
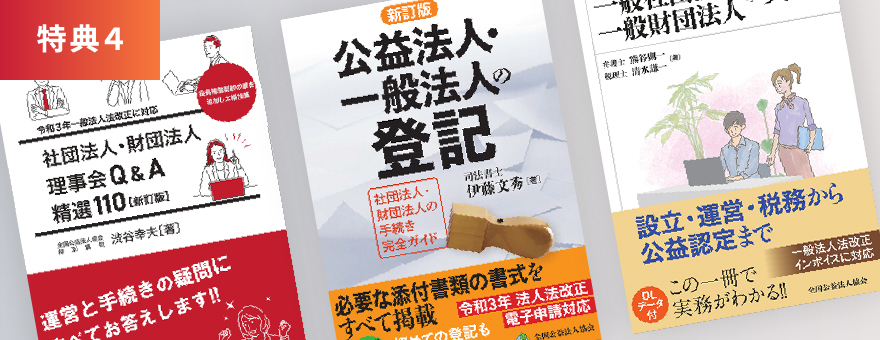
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。