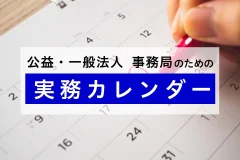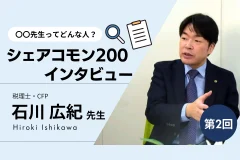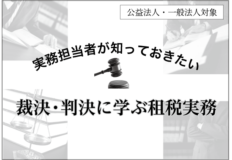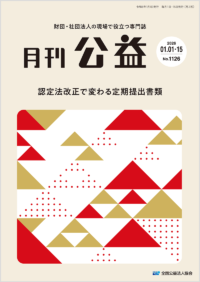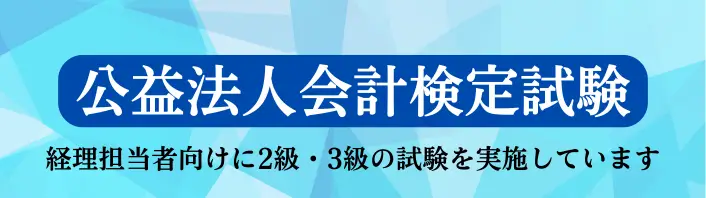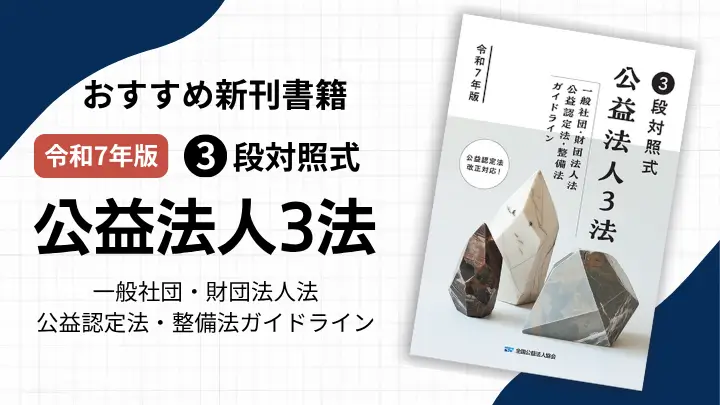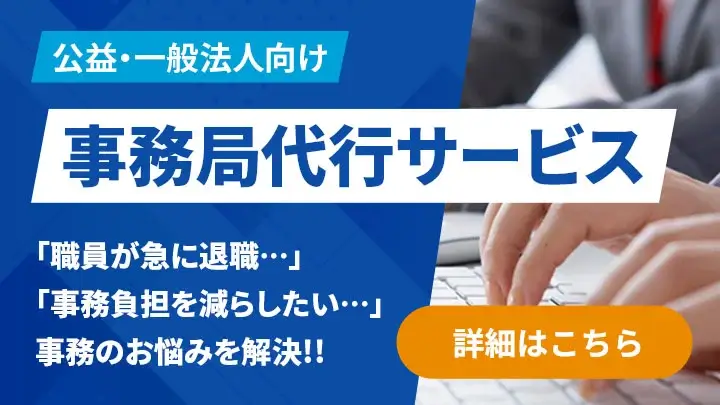労働判例から学ぶ!! 後悔しない雇用契約書
2018年08月30日

石井妙子
(いしい・たえこ 弁護士)
(いしい・たえこ 弁護士)
- CATEGORY
- 労務・雇用契約
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- 契約書作成と就業規則はなぜ必要?
- 契約書に記載すべき事項
- 後悔しない雇用契約書のひな型
- 契約書における項目別留意点
- ・有期雇用契約について
- ・労働時間について
- ・担当業務について
- ・転勤・配置転換について
- ・解雇理由(解約理由)について
- ・守秘義務等について
- ・同一労働同一賃金
契約書作成と就業規則はなぜ必要?
労働契約書の作成は必ずしも必須のものではなく、正職員に関しては、雇用契約書を作成せず、法人からの採用辞令と、本人からの誓約書及び就業規則の周知という形式で対応していることが多い。労働契約法7条は、「合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」としており、そのため労働契約の内容をすべて契約書に定めることなく、詳細は、就業規則の周知をもって対応することが可能だからである。ただし、労働基準法15条は、一定の事項については、雇用に際して書面で明示すべきであるとし、パートタイマーの場合は、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)6条も明示事項を定めているので、所定の事項については、書面の作成が必要であるが、これも双方で署名又は記名押印する契約書であることまでは求められていない。
一方、有期雇用契約職員、パートタイマー等、いわゆる非正規職員については、厚生労働省の様式を用いて、労働条件通知書を作成することが多く、単に交付するだけでなく、労働者本人のサインをもらったり、使用者と従業員の双方が署名捺印して「契約書」としていたりすることも多いようである。非正規職員については、労働時間や担当業務などが個別化されていることもあり、就業規則に、例えば「労働時間は個別に定める」などとしていることが多く、また、有期契約の場合、期間管理を行うために契約書があったほうが良いということがあるため、上記のような対応が多いのであろう。
そのような次第で、従前、雇用契約書の利用については、非正規職員の場合が中心であったが、正職員
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら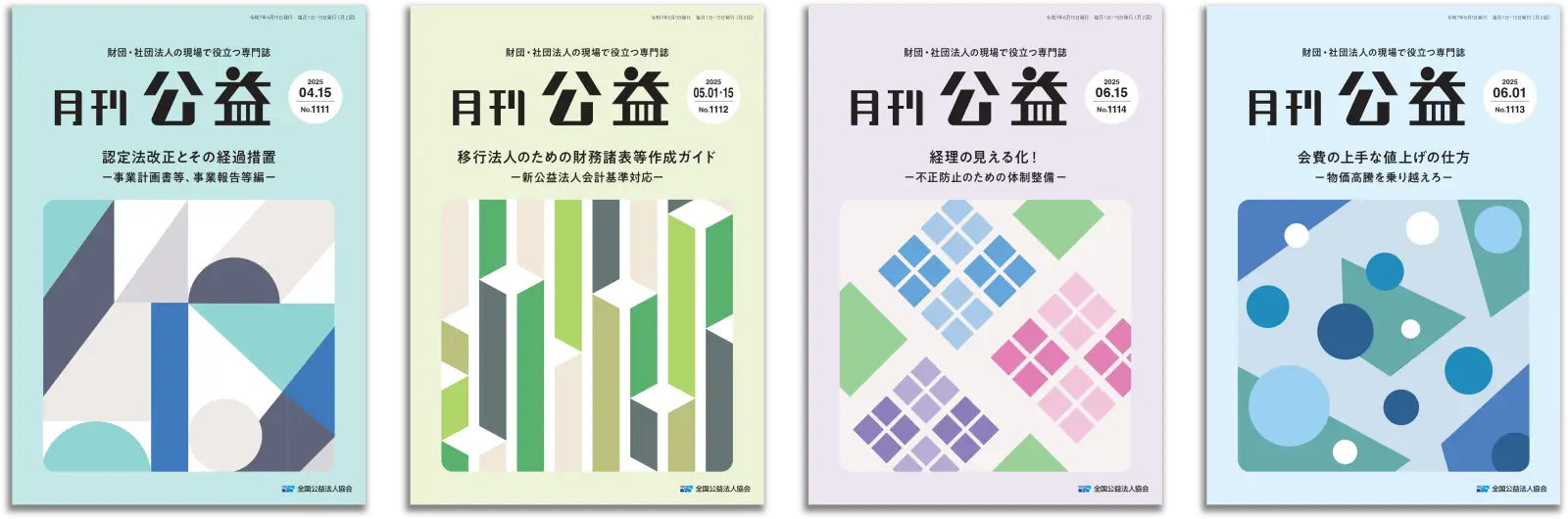
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
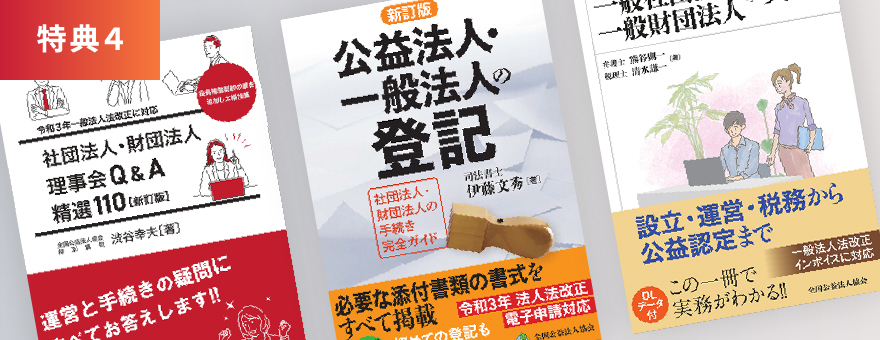
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。