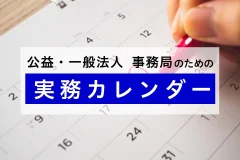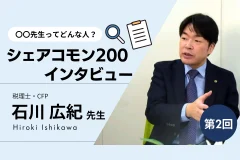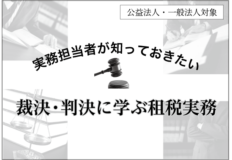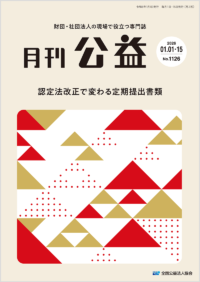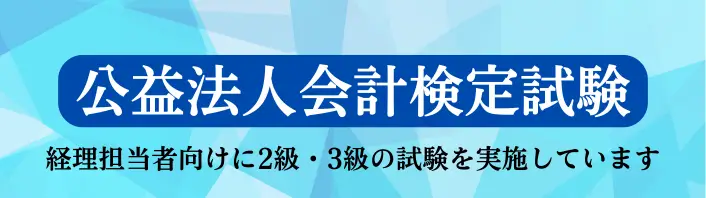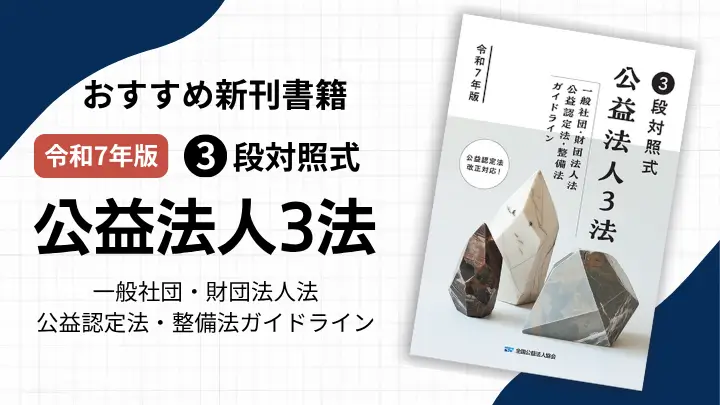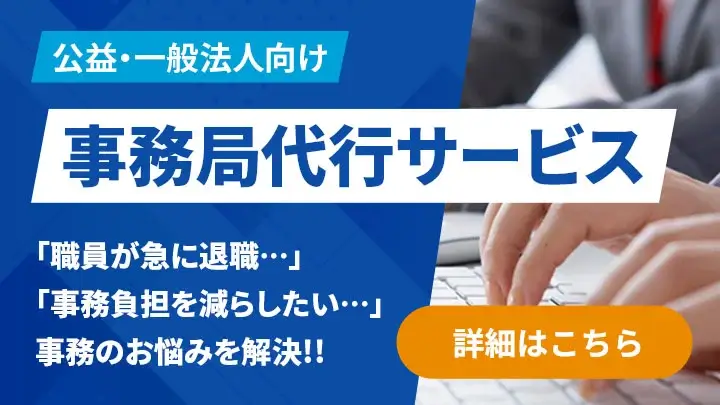正しい役員等の変更登記(上)
2018年11月29日
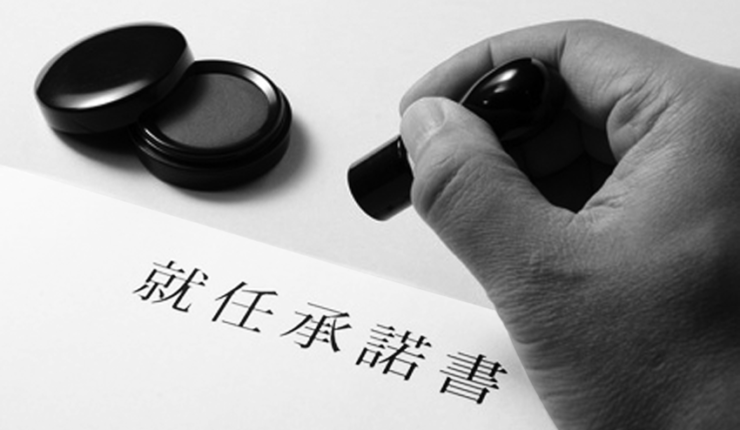
中野千恵子
(なかの・ちえこ 司法書士)
(なかの・ちえこ 司法書士)
- CATEGORY
- 法人運営・変更登記
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- どういった場合に変更の登記が必要となるのか
- 改選による役員等の変更登記
- 改選となる役員等の確認
- 任期途中で辞任又は増員した役員等がいた場合
- 事業年度の途中で選任された役員等の任期満了
- 役員等の変更登記に必要な書類
- 理事、監事、評議員に準備してもらう書類
- 代表理事に準備してもらう書類
- その他の書類(議事録)
- その他の書類(定款)
- おわりに
はじめに
本稿は、理事、監事、評議員(以下、「役員等」という。)及び会計監査人について必要な登記、特に、改選期における定時社員総会又は定時評議員会の終結後に必要な役員等の変更登記について、(上)(下) 2 回に分けて解説する。本稿(上)では、役員等の変更登記に必要な書類等の総論について解説する。役員等の変更登記において、特に質問が多いのが、「押印は実印か認印か」「印鑑証明書は必要か」といったことであるが、それについてもケースごとに解説を行っていく。
なお、理事会非設置の一般社団法人については、本誌の読者に該当する法人はないと思われるため割愛した。
また、公益社団法人・公益財団法人についても、一般社団法人・一般財団法人と同様に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)及び一般社団法人等登記規則が適用され、登録免許税が非課税であることを除けば、登記手続については「一般社団法人・一般財団法人」と同じであるので、本稿では「一般社団法人・一般財団法人」を「公益社団法人・公益財団法人」と読み替えてご参照いただきたい。
どういった場合に変更の登記が必要となるのか
一般社団法人及び一般財団法人については、次の事項を登記しなければならず(一般法人法301条、302条)、これらの事項に変更が生じた場合は、変更の時から2 週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ、変更の登記を申請しなければならない(一般法人法303条)。一般社団(財団)法人の登記事項(一般法人法301条)
❶ 目的
❷ 名称
❸ 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
❹ 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め⑤ 理事の氏名(財団法人の場合は理事に加えて評議員及び監事の氏名が加わる)
⑥ 代表理事の氏名及び住所
❼ 理事会設置一般社団法人であるときは、その旨(財団法人の場合は登記事項でない)❽ 監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名(財団法人の場合は登記事項でない)❾ 会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称⑩ 一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
⓫ 役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
⓬ 非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め⑬ 公告方法を「官報」又は「日刊新聞紙」と定めた場合に、貸借対照表の内容を電磁的方法により提供を受けることができる措置をとることとするときは、貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの(ホームページのURL)⓮ 公告方法
⓯ 公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの(ホームページのURL)ロ 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法(官報又は日刊新聞紙のいずれか)についての定めがあるときは、その定め※ 黒丸数字は定款変更した場合に登記が必要。
【一般財団法人の場合】
一般財団法人の場合、一般社団法人と比べて違うところは、㋐評議員及び評議員会を置く、㋑理事会及び監事が必置である(公益社団法人は、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」により理事会及び監事が必置となるが、一般社団法人は任意設置である。)ことの2 点なので、前記の【一般社団法人の登記事項】のうち、⑤が「評議員、理事及び監事の氏名」となることと、⑦⑧が登記事項ではないことの2 点を除けば、一般社団法人の登記事項と同じである。
ちなみに、定款変更をした場合に登記が必要となるのは、①〜④、⑦〜⑨(理事会・監事・会計監査人の設置に関して)、⑪⑫、⑭⑮に関する規定の変更があった場合のみで、それ以外の定款規定を変更しても、変更の登記は要しない。
【役員等及び会計監査人の場合】
役員等及び会計監査人について、任期満了による改選や任期途中での交代があった場合に役員等の変更登記が必要なのはもちろんのこと、㋐役員等が亡くなった場合、㋑代表理事が住所を変更した場合、㋒婚姻等で役員等及び会計監査人の氏名が変更となった場合にも役員等の変更登記が必要となるので、注意されたい。
㋐ 役員等が亡くなった場合
戸籍謄抄本・死亡診断書・住民票(除票)・遺族から法人に対する死亡届出等のいずれかを添付して、「死亡」を原因とする役員等の変更登記を申請する。㋑ 代表理事が住所を変更した場合
登記手続上は変更後の住所を証する書面(住民票等)の添付は不要である。但し、当該一般社団法人・一般財団法人としては、住民票等の公的書類により事実確認を行う方が望ましいと思われる。㋒ 婚姻等で役員等の氏名が変更となった場合
登記手続上は変更後の氏名を証する書面(戸籍謄抄本等)の添付は不要であるが、前記㋑同様、当該一般社団法人・一般財団法人として何らかの確認書類はあった方が望ましいと思われる。会計監査人については、個人(公認会計士)である会計監査人の氏名変更の場合は添付書面を要しないが、監査法人である会計監査人の名称変更の場合は、その名称の正確性を確認するため、当該監査法人の会社法人等番号を提供するか、登記事項証明書を添付しなければならない。但し、当該一般社団法人・一般財団法人の主たる事務所の所在地と当該監査法人の主たる事務所の所在地が、同一法務局の管轄区域内である場合は、会社法人等番号の提供又は登記事項証明書の添付はいずれも不要である。
なお、㋑代表理事の住所の変更及び㋒役員等の氏名の変更については、改選の際に、当該役員等について変更後の氏名又は住所をもって重任の登記をすることができる(会計監査人の氏名又は名称の変更についてはこの取扱いはできず、名称の変更の登記を要する。)。
改選による役員等の変更登記
役員等の任期満了時を正確に把握していなかったために、必要な選任決議を遺漏し、あるいは不要な選任決議を行ってしまうケースを、時折見受けることがある。特に、任期途中の辞任等により役員の交代があった場合は注意が必要である。まずは、今回の定時社員総会・定時評議員会で、どの役員等が任期満了となるのかを確認するところから始める必要がある。改選となる役員等の確認
役員等及び会計監査人については、一般法人法で、それぞれ「選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会・定時評議員会の終結の時まで」と定められているが、法定された任期を定款で短縮(理事・監事は可能)又は伸長(評議員は可能)することができる。そのため、役員等の任期が何年と定められているかは、必ず、定款で確認するようにする。会計監査人の任期は、一般法人法69条及び197条で「選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。」と定められており、短縮も伸長もすることはできない。
任期途中で辞任又は増員した役員等がいた場合
任期途中で辞任等により退任した役員等の補欠として選任された役員等、又は、増員された役員等がいた場合、当該補欠又は増員役員等について、いつ任期満了となるかは注意が必要である。役員等の種類、定款規定の有無、その他に一般社団法人か一般財団法人かによって、在任の役員等と同時に任期満了するか否か結論が異なってくる。そのため、当該補欠又は増員役員等の任期満了する時は、登記事項証明書(「現在事項証明書」ではなく、「履歴事項証明書」が良い。)、定款、当該補欠又は増員役員等を選任した際の議事録を準備して確認を行う。【補欠の役員等について】
◇理事の場合
一般社団法人の場合、理事の任期は、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することができる(一般法人法66条)。そのため、定款に「任期満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。」といった規定がある場合はもちろんのこと、定款にこのような補欠規定がない場合でも、後任理事を社員総会で選任する際に、「任期を前任者の任期が満了する時までとする。」といった内容で決議している場合には、後任理事は前任者の任期を引き継ぐことができる。
一方、一般財団法人については、一般法人法177条において、一般法人法66条ただし書中「定款又は社員総会の決議によって、」を「定款によって」と読み替えて準用している。そのため、評議員会の決議によっては、前任者の任期を引き継ぐといった内容で決議することはできず、定款に「〜補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。」といった記載がされていない場合は、前任者の任期を引き継ぐことはできない。
◇監事の場合
監事の任期については、定款に「任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。」といった規定がある場合のみ、前任者の任期を引き継ぐことができる。
◇評議員の場合
監事同様、定款に「任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。」といった規定がある場合のみ、前任者の任期を引き継ぐことができる。
【増員された役員等について】
◇理事の場合
一般社団法人の場合、補欠の理事と同様に、増員された理事についても、定款又は社員総会の決議によってその任期を短縮することができる(一般法人法66条)。例えば、定款に「増員された理事の任期は、他の在任理事の残任期間と同一とする。」といった規定がある場合や、社員総会で選任する際に増員理事の任期を「他の在任理事の任期が満了する時までとする。」といった内容で決議している場合には、当該増員理事は、他の在任理事と同時に任期満了することとなる。
一般財団法人については、評議員会の決議によって理事の任期を短縮することができないので、定款に増員理事の任期に関する規定がない場合は、増員理事の任期を他の在任理事の残任期間と同一とすることはできない。
◇監事の場合
増員監事の任期を他の在任監事の残任期間と同一とすることは、当該増員監事の任期を短縮することと同じである。監事の任期の短縮は、前述のとおり、定款に補欠の監事についての規定がある場合のみ可能である(一般法人法67条2 項、177条)。
したがって、増員の監事の任期については、定款に定められたとおりの任期(選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会・定時評議員会の終結の時まで)となり、他の在任監事の残任期間と同一とすることはできない。
◇評議員の場合
評議員についても、監事の場合と同様、任期の短縮は定款規定に基づく補欠の評議員についてのみ可能であるため(一般法人法174条2 項)、増員評議員の任期を他の在任評議員の残任期間と同一とすることはできない。
補欠役員等が前任者の任期を引き継ぐために必要な要件及び増員役員等の任期を他の在任役員等の残任期間と同一とするために必要な要件
事業年度の途中で選任された役員等の任期満了
定時社員総会・定時評議員会ではなく、事業年度の途中で選任された役員等の任期の計算については、少し注意が必要である。「選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会・定時評議員会〜」とは、選任から○年後の定時社員総会・定時評議員会ではなく、「『選任から○年経過した時点で終了している事業年度のうち直近のもの』に関する定時社員総会・定時評議員会」のことである。そのため、選任の時期によっては、「選任後2 年以内〜」の任期であっても、約1 年で任期満了となるケースもある。なお、役員等の人事に変更が無い場合であっても、定款で定めた任期が満了した時は、再度、定時社員総会・定時評議員会で選任(再任)の決議をし、役員等の変更登記を申請しなければならない。時折、任期満了による改選の前後で役員人事に変更が無い場合、定時社員総会等で選任の決議はしたものの、役員等の変更登記申請がなされていないことがあるので注意されたい。
役員等の変更登記に必要な書類
次に、役員等の変更登記に必要な書類につ月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら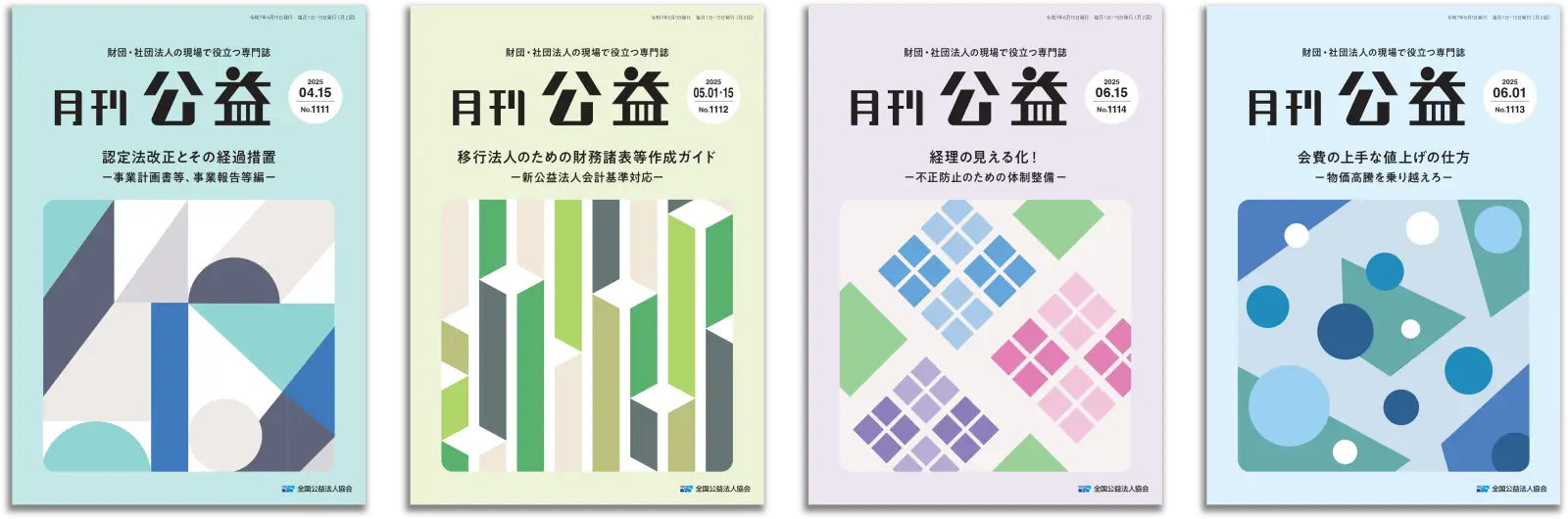
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
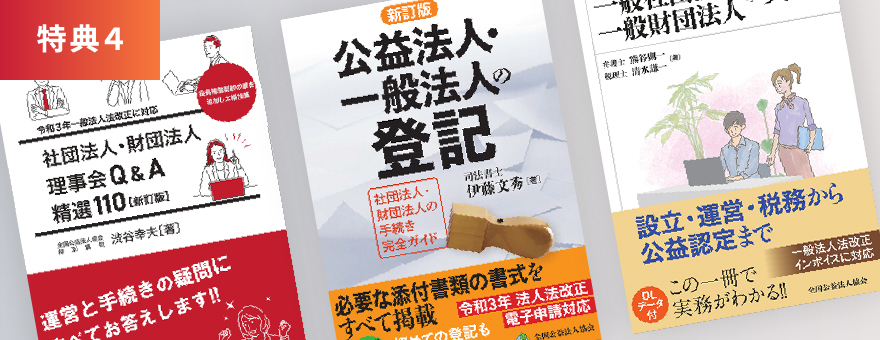
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。