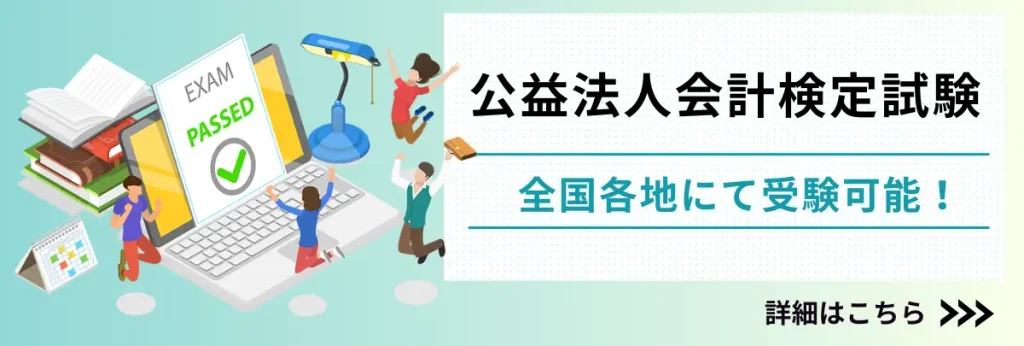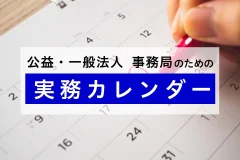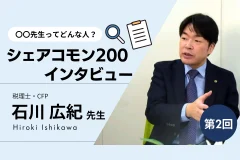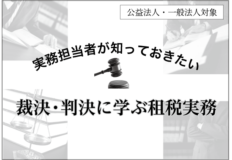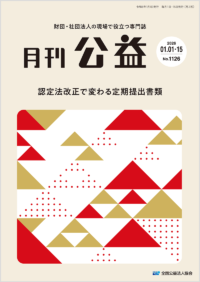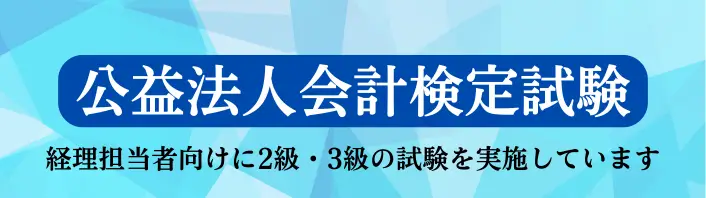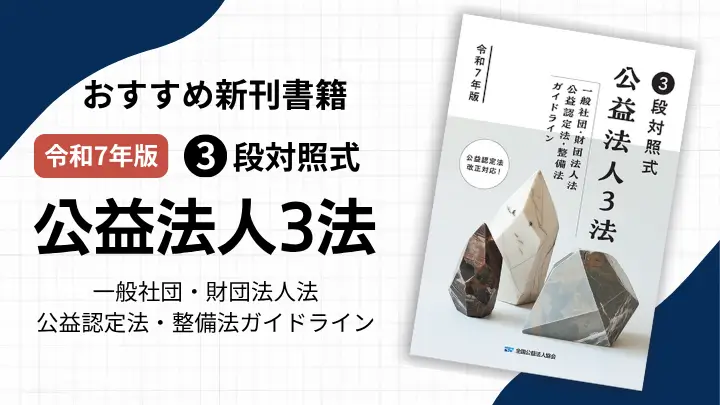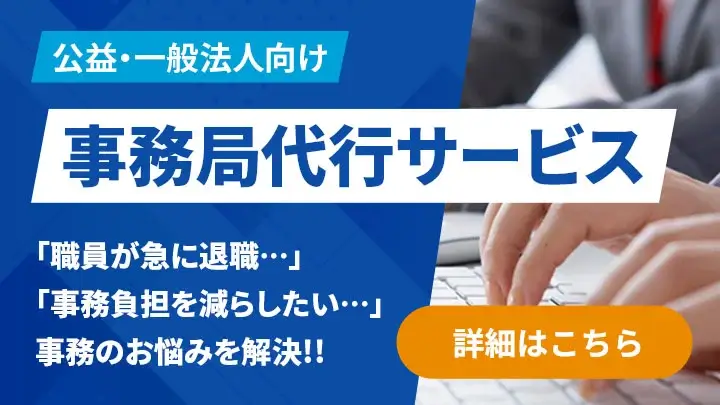其之一 会計バカ、参上!!

(ふるいち・ゆういちろう 大原大学院大学准教授)
オレは会計バカなんだっ!!
現在、私は都内の会計専門職大学院で簿記、会計関係の科目を担当している。
この仕事をしていると「なんで、大学の先生になろうと思ったんですか?小さい時から勉強が好きだったんですか?」という質問をたまに受ける。その時には、正直に「大学2 年生の時に毎朝9 時に会社に行くだけの社会性が自分には備わっていないことに気づいたからです」と答えている。
社会性が欠落している自分にも務まる仕事は、何か?と考えて、気がついたら今の職業に就いていた。ただ、働き始めて分かったことだが、この業界には、私よりもはるかに会社勤めに向いてなさそうな人物が多いのである。しかも私も含め各々が自分だけはまともだと思っているから始末が悪い。
大学院で会計学を教えていると言うと多くの人は、「お金の管理とかきちっとされているんでしょうね?」と言ってくださるが残念ながら不正解だ。必ずしも哲学者が幸せになるとは限らないのと一緒である。
たとえば、会計は基本的には、お金の計算の学問であるが、ほとんどの会計学者は、お金の計算が苦手で、会計学者同士の飲み会はお会計が合わずに大パニックというのは日常茶飯事だし、大学に提出する経費の精算の書類を作成させればほぼ確実にミスをする。
会計記録には、規則性を求める一方、自分は昼夜逆転した不規則な生活を送り周囲を困らせる。一番の被害者は、大学の事務職員と出版社の皆様だろう。
そんな私に、編集部から「会計学にまつわるエッセイを書かないか?」と声をかけていただいた。月に1 回、エッセイの連載を持たせていただけるとは、過分な評価である。本業はイラストレーターでありながらエッセイでの高い評価が得られるような、みうらじゅん状態に持ちこめば、私も会計学者でありながらエッセイ作家としての高評価を得る千載一遇のチャンスである。
やはり打合せは、銀座の高級クラブで行うのか? 筆が進まない時は、ホテルの一室が用意され至れり尽くせりの環境で原稿を書くのか? そんな私の妄想を他所に担当者からメールで提案されたタイトルは「会計バカ一代」。
本誌で制度解説を書かれているような先生方には、絶対こんなタイトル提案しないだろ!?と内心思ったが、初心に帰り、まず自分は会計バカであるということを認め、少しでも世間の常識的感覚を取り戻そうと思い、謹んで連載を担当させていただくことにした。
芸能人に説明責任なんてない!!
さて、会計学者の多くは、会計が社会の中で最も重要視されるべきことだと思い込んでいる。そのため世の中で会計にまつわる専門用語が正しく使われていない時など、その事が気になって仕方がなくなる。
例えば、現在、いろいろな場面で「説明責任」という用語が使われているが、多くの場合、会計で用いられるのと異なった意味で使われており、会計学者をヤキモキさせる。この「説明責任」(アカウンタビリティ)という用語は元来、会計用語であり、英語で「会計」を意味するaccountingは、「説明する」というaccountを語源としているとしばしば説明されることからも分かるように、会計においては、極めて重要な概念である。
一例として、ある芸能人がスキャンダルを起こしマスコミが路上でその芸能人を捉まえて「ファンの皆さんへの説明責任をどのようにお考えですか?!」と詰め寄っているというワイドショーでのお約束のシーンを考えてみる。ここでの説明責任とは「ファンやマスコミに向けて説明する責任があるんだから納得できる説明をしてほしい」くらいの意味で使われていると思われるが、会計用語的にいえばその芸能人に説明責任は存在しない。
会計における「説明責任」とは財産の提供者とその受託者の間に成立する責任のことである。会社でいえば、株主に対して経営者が負っている責任であるし、非営利組織でいえば、寄付者に対して組織の運営者が負っている責任であるといえる。
そして、この「説明責任」において重要なことは、発生した責任についてその責任を解除する方法が同時に備えられている点にある。つまり、資金の受託者が提供者に対して説明を行い、資金の提供者がその報告を承認することで責任の解除が行われるのが、本来の説明責任である。
この意味で芸能人に説明責任があるからコメントをしろというのは、用語の使い方として間違っている。それは、芸能人に対し全国民が資金提供をしてないかぎり、責任は存在しない。さらに言えば、それを解除する明確な手続きも存在しない。実際には、芸能レポーターがその話題に飽きるのを待つしかないのだ。
会計こそが森羅万象を司る!!
仮にわれわれの税金で活動する「国営アイドル」なんかがいて、国会の議決を経た国民との約束(熱愛禁止、結婚宣言禁止等)を破ったケースがあれば、「説明責任」が生じるのかもしれないがそれは、かなりのレアケースになるであろう。
このように会計学者は日常のちょっとした専門用語の使い方にも噛み付かないではいられない人種である。会計は、社会生活に深く根ざしているのでその用語もいろいろな意味で使われるようになるのは当然だ。しかしながら会計学者にとっては、会計こそが森羅万象を司るシステムであり、ちょっとした言葉の転用も気になってしょうがないのである。
そんな事を気にする前に大学に提出する経費の精算書類を自分で正確に作成できるようになるのが先な気もするが、それは私にとって会計の歴史をラテン語で学ぶよりもはるかに難しいことなのだ。そんな私は会計バカ。
ふるいち・ゆういちろう/専門は非営利組織会計、学校会計、公会計、財務会計。
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら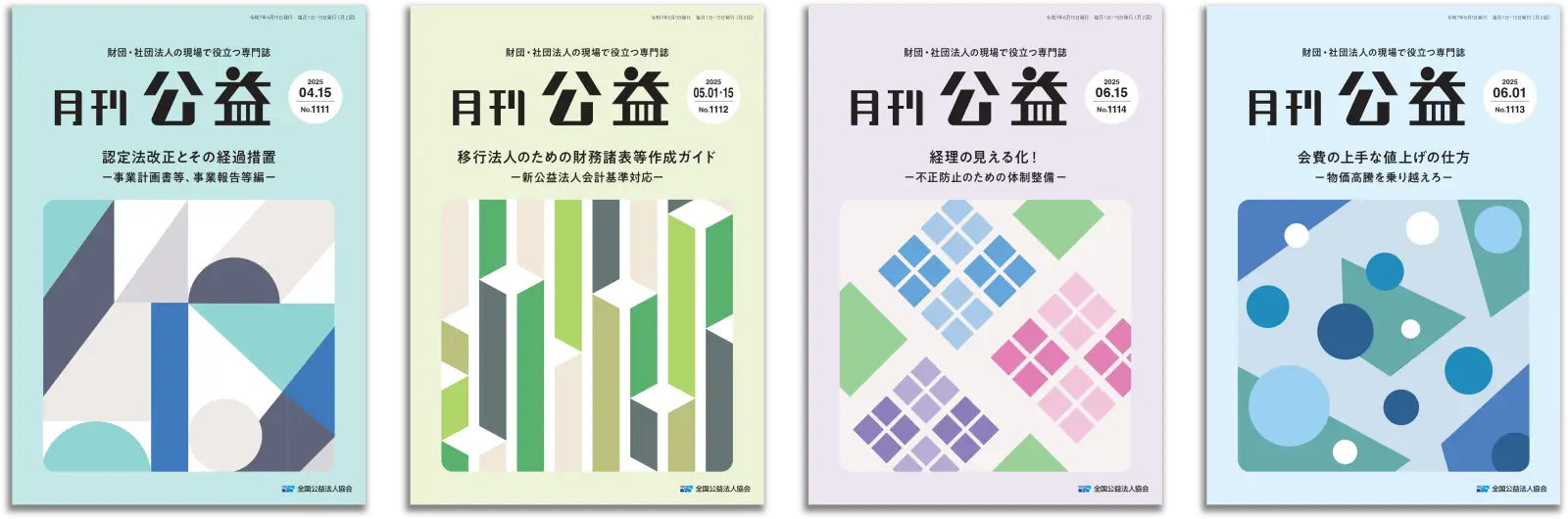
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
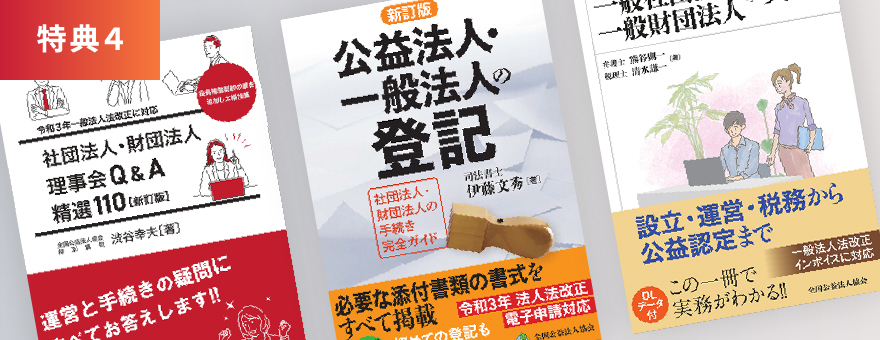
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。