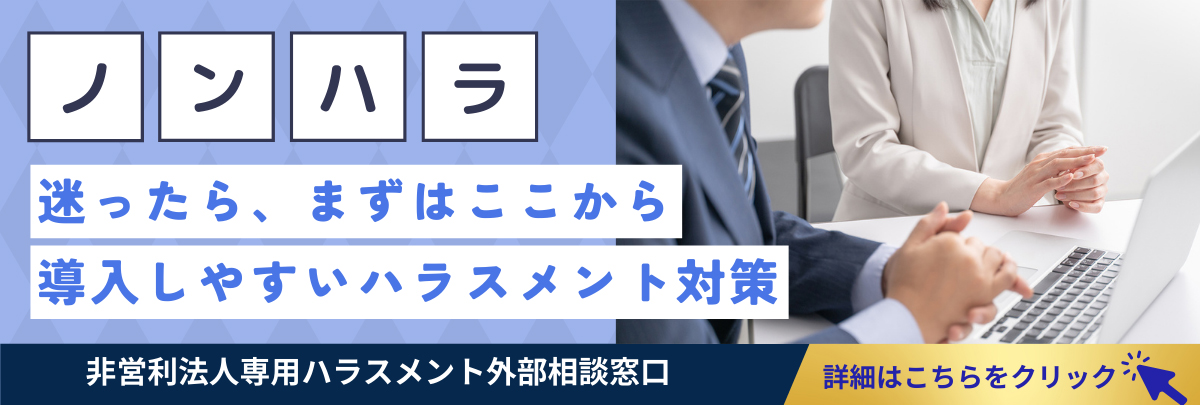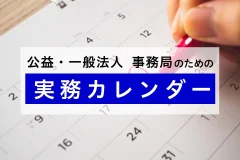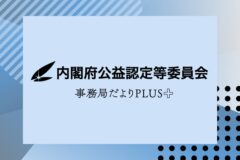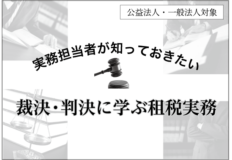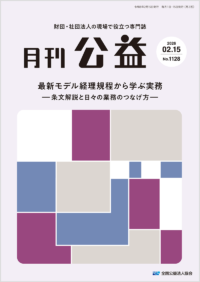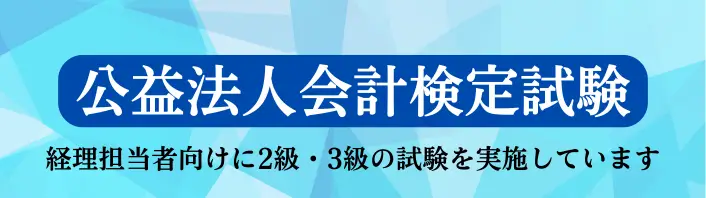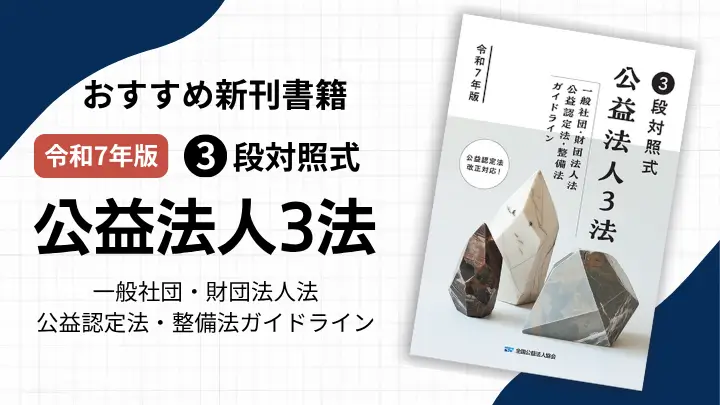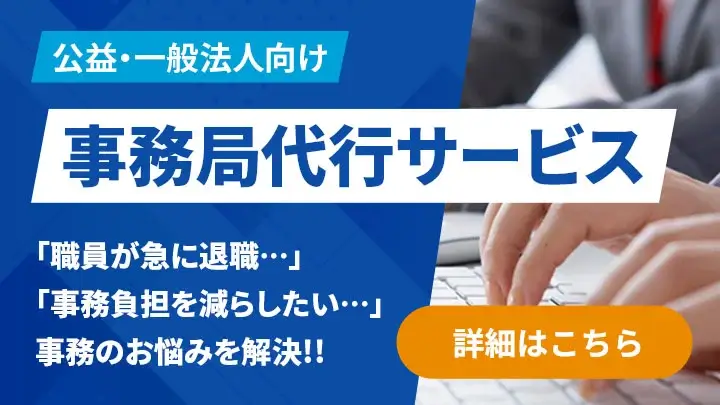第1回 ハラスメントは他人事ではない ─ 事例から学ぶリスクと対策
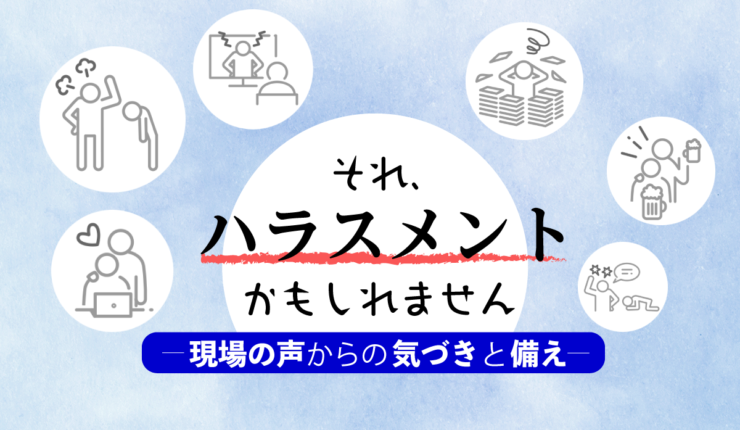
(みやもと・つよし メンタル・リンク代表取締役社長・公認心理師・シニア産業カウンセラー)
本連載では、心理職として数多くの法人に携わってきた筆者が、実際の事例や現場の声をもとに、ハラスメントに「気づくこと」、そして「備えること」の大切さを、公益法人、一般法人の皆様にお届けすべく全4回にわたりお伝えします。
F社の報告書から浮かび上がるハラスメントリスク
ハラスメントは全ての職場で防止措置が義務づけられているにもかかわらず、「どう対応すればよいか分からない」と感じている法人は少なくありません。特に小規模な公益法人では体制の整備が追いつかず、実際の対応に不安を抱える声が寄せられています。どんなケースがハラスメントにあたるのかイメージがわかない方も多いようです。そこでこうした現場の声に基づき、本連載第1回では社会的に問題となっているF社の事案をもとに、ハラスメントが発生するイメージをもっていただければと考えています。
ハラスメント問題は、大手企業等で発生するとニュースで大きく取り上げられます。F社の問題では第三者委員会がまとめた394ページに渡る報告書が公表されました。報告書を紐解くと、そこにはどの組織でも起こりえるハラスメントの兆候が散見されます。F社の事案を参考に、ハラスメントリスクについて考えていきましょう(筆者がF社問題に介入しているわけではなく、あくまでも報告書の記載を元に執筆。また、本稿でのアルファベット表記は報告書のアルファベットと同一ではありませんのでご留意ください)。
F社の問題から教訓にできること
元社員のA氏が元芸能人のX氏から「性暴力」を受けたこと、F社では他にもハラスメントがあったことが認められました。A氏がPTSD(心的外傷後ストレス障害)になるほどの衝撃的な内容で、それをきっかけに不同意性交についても注目されています。
当然ですが、「性暴力」はあってはならないことです。そのため、法人としても職員に注意喚起を行うことが必要です。何よりも、大事な職員の心身の安全を守る義務があります。一方で、「さすがにここまで大きな問題は職場で起きないよ」という声も聞きます。
しかし、報告書を読むと、今回の事件に至るまでにもさまざまな問題点があると感じられます。大きなハラスメントの前には、前兆となるハラスメントや問題が起きていることが多いものです。そういった前兆をキャッチすることがハラスメントが起こらない職場づくりにつながります。なお、「ハラスメント例」はさまざまな事例等から架空の内容を作成しました。
日頃から男、女と性別で括るようなことは無自覚なセクハラを生み出す風土を作りだしてしまいます。
例えば、取引先との懇親会で「女の子が社長の周りを囲まないと……」と取引先の社長の隣を促す等の言動です。F社問題でその兆候が見られるのは、女性に対して「喜び組」と呼んでいる点です。そもそも、「喜び組」と言っている時点で問題ですが、放置していると、いつの間にか大きなハラスメントに発展してしまいますので注意が必要です。
ハラスメント例
対 策
男性・女性には生物学的な違いはありますが、性別で括るのではなく、個人で捉えることを日頃から心がけましょう。例えば、「今日は〇〇さんを呼びたいね」等です。
A氏に対して権限のある社員B氏が飲み会に参加することに対して「仕事でプラスになる」と言っていたようです。優位な立場の人の発言は心理的な拘束が強く要注意です。「仕事でプラスになる」と言われてしまえば、クライアントに時間外・休日に誘われた際に断りづらくなります。法人でも組織として注意が必要です。
ハラスメント例
対 策
時間外で業務との関係性が希薄な懇親会等についての要求は、あらかじめ上司や先輩から「原則お断りします」「もし参加させてもらう時には3 人以上で参加させてもらいます」と伝えておくことが対策の1 つとなります。どうしても職場として仕事の一環ということで時間外に懇親会に行かせるのであれば、仕事として残業代等を支払い、その上で上司も同席するといいでしょう。繰り返し要求してくる場合には、上司から先方役員・理事に正式に断りを入れることも必要です。
F社の報告書を読むと、第三者委員会が大事な指摘をしています。PTSDになった被害者の対応を専門家ではないC氏にまかせっきりにしたことで、C氏を精神的に追い込んでしまったという点です。
ハラスメント例
対 策
職員1人にまかせっきりにせず、公認心理師を含めた専門家を入れる、また窓口は1人としても複数で協議する体制を作ることが大切です。
F社では相談しても秘密が守られず社内に情報が漏洩してしまうリスクがあるというような声が報告書に記載されています。秘密が守られないことが事実かどうかは別としても、そのようなうわさがあると、誰も相談しなくなり、事態が深刻になることがあります。
ハラスメント例
対 策
日頃から秘密を漏らさないように徹底する必要があります。個人の情報(「先輩は、最近合コンで彼女見つけたらしいですよ」「課長は最近離婚したらしいよ」「Hさん、不妊治療しているようだよ」等)や家族の情報(「あの人の旦那さん、○○商社の取締役らしいよ」等)を勝手に漏らさないこと等が重要です。
公益・一般法人でハラスメントが生まれやすい3つの気づき
ここまでF社の報告書で浮かび上がったハラスメント事案を参考に、法人でも起こり得るハラスメント事例とその対策を見てきました。公益法人や一般法人は法人規模が小さなところが多く、時には独特の文化が醸成されることもあり、それが行き過ぎるとハラスメントを生み出す要因になりかねません。気づきとして3 つのポイントを紹介します。
職員数が少なく、密な人間関係が生まれやすい
公益法人の職員数は平均5 名と少なく、加害者と被害者を離すこと(異動)が難しい上、問題が周囲にすぐ知られてしまうおそれがあります。理事長らに権限が集中しやすく、意見を言いづらい環境もハラスメントを指摘しにくくしています。
ベテラン職員が多く、新しい価値観の浸透が遅れがち
ベテランの影響力が強く、時代にそぐわない暗黙のルールが残りやすい傾向があります。たとえば、特定の人の意見が絶対視されたり、性別による役割分担が当然とされることがあります。
社会貢献の名のもとにやりがいの搾取が起こるリスクがある
「営利企業ではない」「公益性を大切に」といった理念が、自己犠牲の強要につながる場合があり、それゆえにハラスメントの温床になる可能性があります。
次回は具体的に公益法人でハラスメントが生まれる要因を考察しながら、防止策を解説していきます。
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら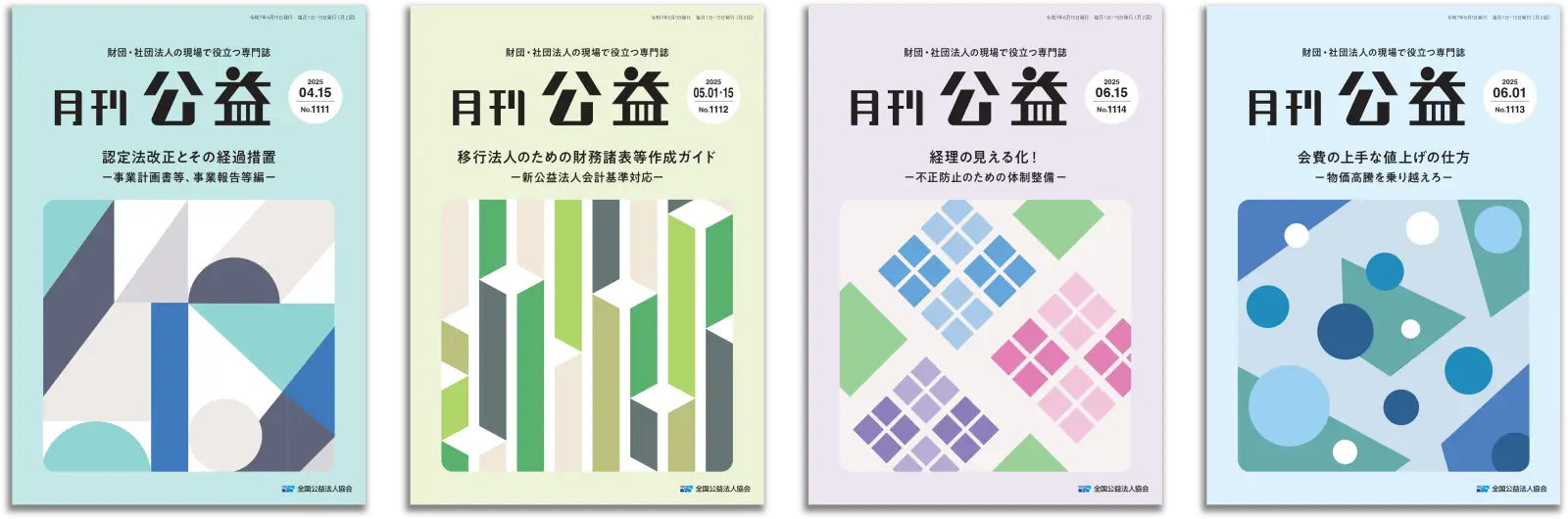
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
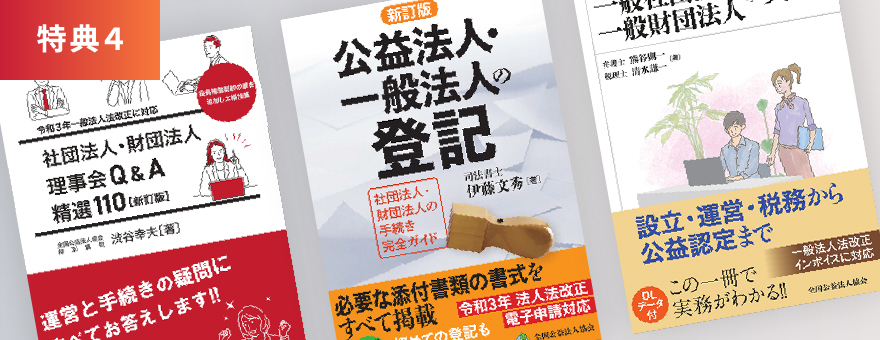
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。