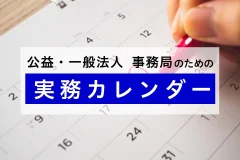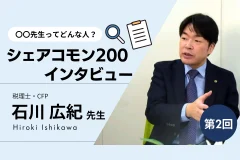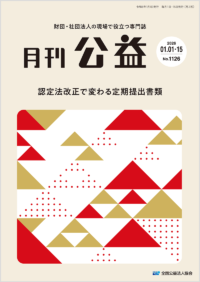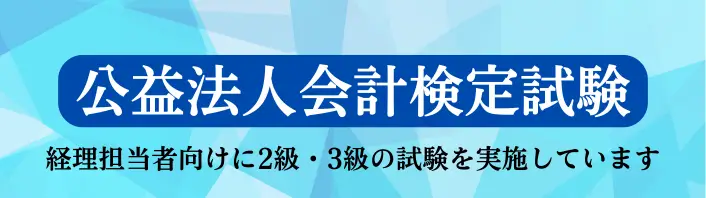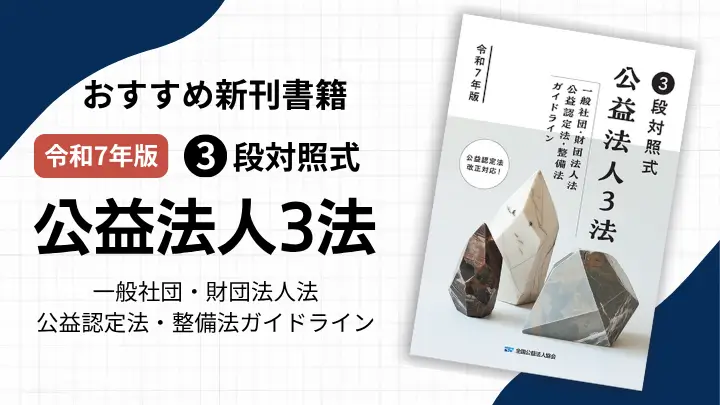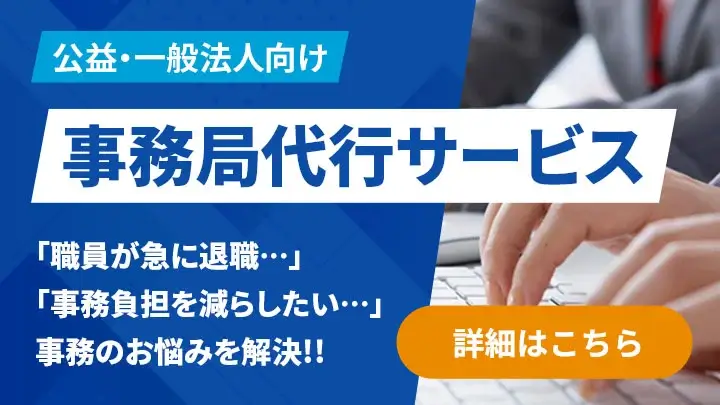公益法人会計基準の改正で「正味財産増減計算書」は「活動計算書」へ

(やました・ゆうじ 税理士)
公益法人会計基準が見直され、「正味財産増減計算書」は「活動計算書」へと変更されます。この変更は、企業会計との乖離を埋め、より分かりやすい財務情報の提供を目指したものです。従来の書式との違いや、新様式の特徴をわかりやすく解説します。
1.改正の背景と目的
これまでの公益法人会計は企業会計と比較して分かりにくいと言われていました。わかりやすい財務情報の開示を実現するために、公益法人特有の会計処理を見直し、「正味財産増減計算書」から「活動計算書」へと組み替えられました。
「正味財産増減計算書」に慣れた方にとっては、「活動計算書」へ変更になったことで、作業効率が下がるなどの意見もあるようです。しかし、公益法人会計に慣れていない方にとっては、活動計算書と3種類の注記情報によって段階的に詳細な情報へ掘り下げていくことができます。概要のみを把握したいのであれば活動計算書の簡潔な記載で目的は達せられます。
一方で、詳細な情報を求めるのであれば、3種類の注記情報で角度を変えた財務情報を確認することが可能となります。活動計算書の作成段階では利便性は認識できないかもしれませんが、役員等への説明の段階になると説明しやすさという利点を体感できると思います。
2.正味財産増減計算書からの主な変更点
⑴ 活動計算書
正味財産増減計算書は、財源別に指定正味財産の部と一般正味財産の部を区分していました。指定正味財産の指定を解除し、一般正味財産に振り替えて使用するという流れが、分かりにくいとされていました。活動計算書では財源別の区分は行わないで、法人全体での損益状況を簡潔に把握できるようになっています。
正味財産増減計算書の一般正味財産の部は「経常増減の部」と「経常外増減の部」に区分されていました。これは、通常反復的に発生する取引を「経常増減」とし、それ以外の非反復的・特殊性の高い取引を「経常外増減」として認識していました。
活動計算書での「経常活動区分」と「その他活動区分」は、経常的な活動として発生した取引であれば、発生頻度が低くても経常活動区分に記載することになります。
【活動計算書】

出典:内閣府「第72回 公益法人の会計に関する研究会議事次第及び資料」を基に筆者加工
⑵ 内訳書は注記情報
正味財産増減計算書内訳表に記載されていた会計区分及び事業区分の損益情報は、活動計算書の財源区分別内訳の注記における一般純資産区分について注記することになります。
⑶ 財源区分別内訳
正味財産増減計算書は、財源別に指定正味財産の部と一般正味財産の部を上下で区分していましたが、財源区分別内訳では左右に区分することになりました。
これまでは指定正味財産の指定を解除し一般正味財産に振り替えて使用するという区分変更が行われていましたが、新会計基準では原則として指定純資産から一般純資産への振替は認められません。
ただし、資源提供者から使途の制約を受けた資源である指定純資産について、やむを得ない事情により指定された使途に使用できなくなった場合には、指定純資産から一般純資産への振替が認められます。
【活動計算書の注記 財源区分別内訳】

出典:内閣府「公益法人会計基準の運用指針 令和6年12月」を基に筆者加工
⑷ 会計区分及び事業区分別内訳
上記の活動計算書の財源区分別内訳注記における一般純資産区分について、会計区分及び事業区分別の内訳を注記します。これまでの正味財産増減計算書内訳表に相当するものとなります。
【会計区分及び事業区分別内訳 活動計算書 一般純資産の部】

出典:内閣府「公益法人会計基準の運用指針 令和6年12月」を基に筆者加工
⑸ 事業費・管理費の形態別区分
事業報告に係る定期提出書類の別表F(1)、(2)に相当するものとなります。新基準では、法人会計に計上される管理費の例示が明らかになっています。これまで管理費に計上していた費用の見直しの機会にしていただけると良いと思います。
【管理費の例示】
【事業費・管理費の形態別区分】

出典:出典:内閣府「公益法人会計基準の運用指針 令和6年12月」
3.スケジュールと実務対応
⑴ 適用時期
新基準は、令和7年4月1日以降に開始する事業年度から適用となります。ただし、令和10年4月1日前に開始する事業年度までは、新基準によらず従前の会計基準を引き続き適用することができます。
⑵ 実務対応
新基準は令和7年4月1日以降に開始する事業年度から適用することになっていますが、多くの公益法人で令和7年度は新基準ではなく、従前の会計基準で処理を行っているようです。
公益法人会計基準に準拠した会計ソフトでは、令和7年の秋くらいから順次対応するような情報があります。したがって、早い法人でも令和8年度からの適用と考えられます。
一方で、今回の公益法人会計基準の改正は、様式の変更がほとんどであって、日常業務での伝票起票などへの影響は少ないと考えられます。会計ソフトで集計した結果である残高試算表をベースに、エクセルで決算書の形式に作り替えている法人にとっては、エクセルの様式を変更するだけで済むことも考えられます。決算書の作成がエクセル中心となっている法人にとっては、会計ソフトのバージョンアップは必須ではないかもしれません。
4.小規模法人などの負担軽減措置
公益目的事業がひとつであって、収益事業等がない場合には、「会計区分及び事業区分別内訳」を作成しないことができます。
5.活動計算書に関するよくある質問(FAQ)
税理士・行政書士。全国公益法人協会相談室顧問。税理士試験試験委員。平成18年に山下雄次税理士事務所を設立。著書に『チャットでわかる社団・財団の経理・総務の仕事』(全国公益法人協会)等。
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら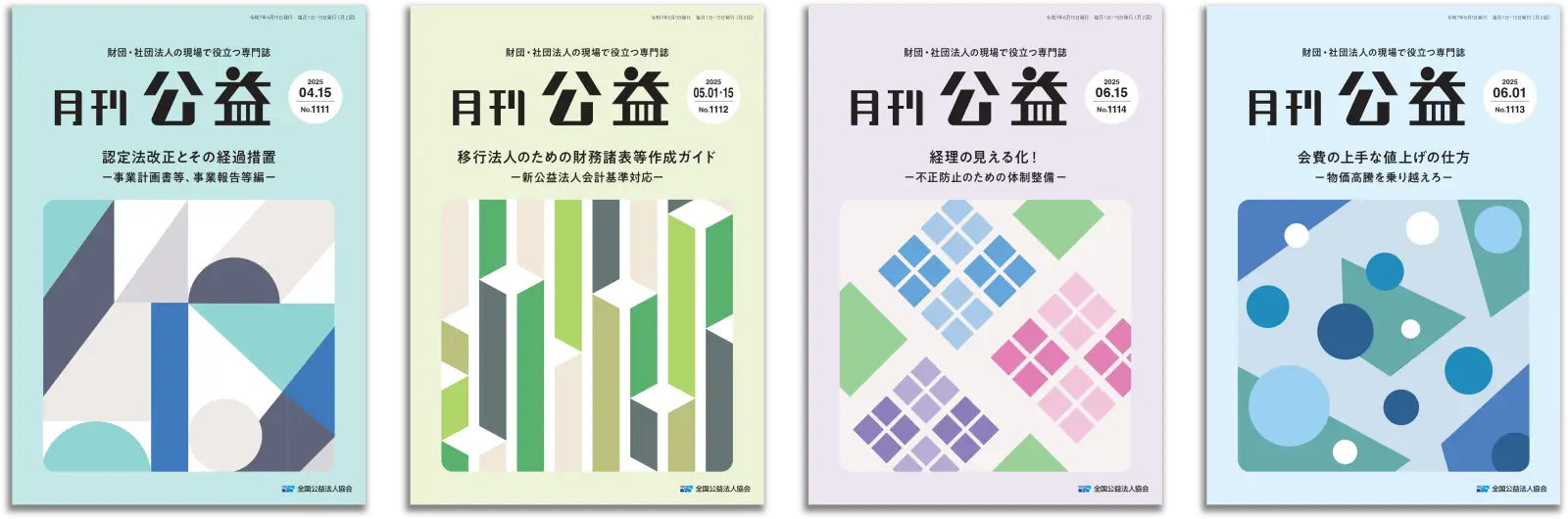
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
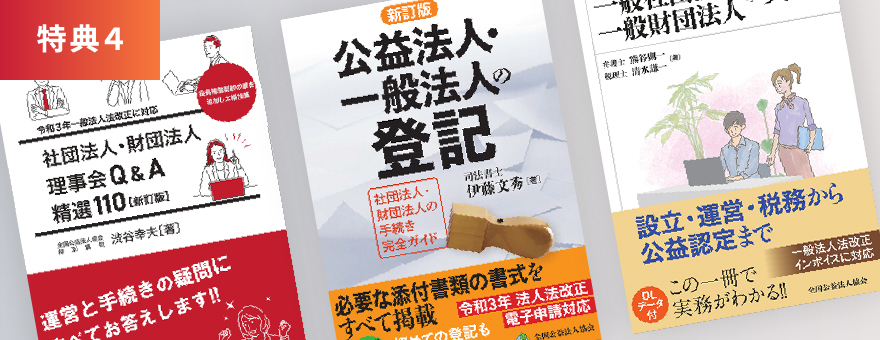
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。