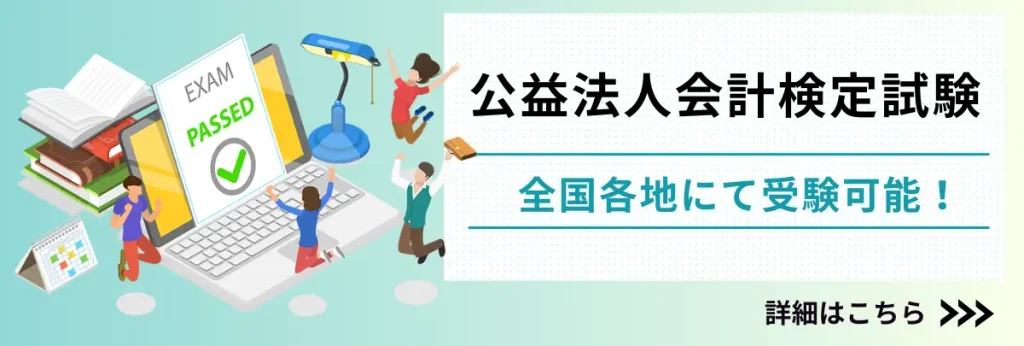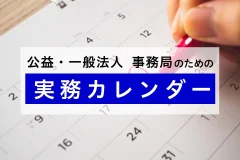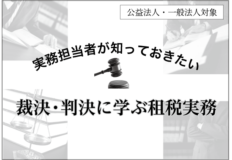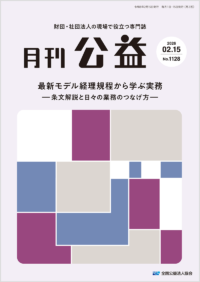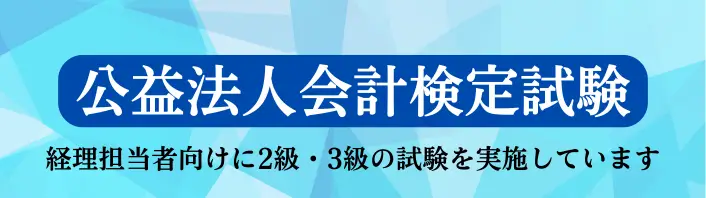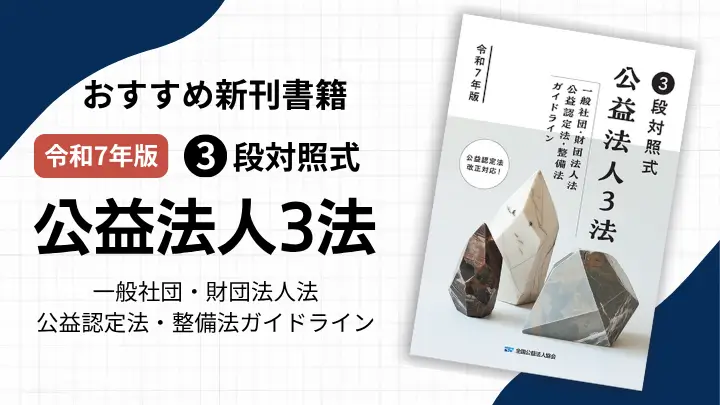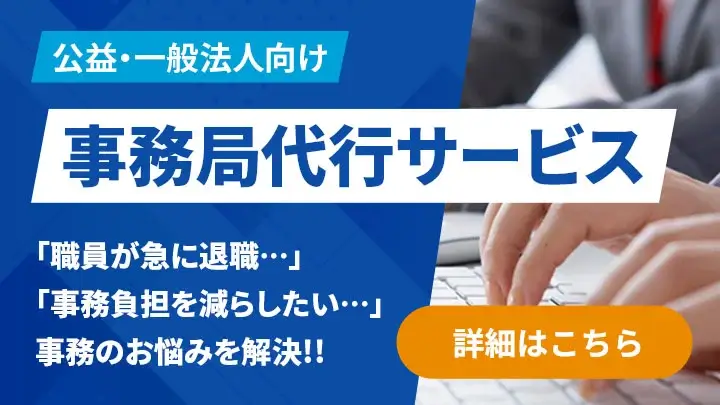其之三十九 検定試験で知識を深める!!

(ふるいち・ゆういちろう 大原大学院大学教授)
講義だけでなくテストもオンライン!!
大学においては、オンライン講義が中心となり、講義を担当する教員にも学生にも変化が求められている。とりわけ、大人数の講義は通常講義の再開の目途が立ちにくく、しばらく不便を強いられそうな状況である。
筆者の場合、オンライン講義の対応が必要な科目については講義の映像を録画し、それを配信する対応を取っている。最近になってようやく映像の収録や資料作りに慣れてきたところであるが、成績評価の根拠となる試験をどのように行うかという問題は今もって悩ましい。
特に難しいのが簿記の科目の試験をどのように行うのかという点である。簿記に限らず、計算能力を育成するような科目においては、限られた時間の中で実際の問題を解く能力を養成する必要があり、試験もその観点から行われる必要がある。
現状においては100人超規模の講義について大学の教室で筆記試験を行う事は現実的で無い。オンラインで試験を実施してもよいが、限られた時間に同じ条件で試験を行う事をこちらで確認する事は難しく依然として課題は残る。
検定試験もオンライン化?!
同様の問題は、簿記の検定試験においても起きているようで、その対応策として日本商工会議所の簿記検定試験においてもネット試験方式が導入されるという。
ネット試験と言っても自宅で受験できるわけでは無く、あらかじめ定められたテストセンターにおいて受験者ごとに異なる試験問題がインターネットを介して受験者のパソコンに配信され、受験者はパソコン上で解答を入力することで試験を実施するのだそうだ。
なお、日本国内で米国公認会計士(USCPA)の受験を行う場合には、すでにこのような試験の方式が導入されており、受験生は会場となるテストセンターに出向き、パーテーションで区切られたスペースに設置されたパソコンで解答を行い試験を受けるシステムになっている。USCPA試験の経験者によると個別のブースに入る前には持ち物のチェックなどが厳格に行われるなど試験の公平性を確保するための仕組みが整っているのだそうだ。
今後は、他の分野における各種の資格試験や検定試験においてもこのような仕組みが広がっていくかもしれない。
日本では、大学で経済学部や経営学部、商学部といったいわゆるビジネス系の学部に入学した新入生や社会人になって初めて経理や会計の知識を習得する必要になった人に対して簿記検定の受験が勧められることが多い。筆者も大学入学直後に簿記検定3 級の試験を勧められ、一夜漬けで知識を詰め込んだ結果、試験当日に寝坊して受験放棄により不合格という挫折を経て現在に至っている。
それ以来、簿記が嫌いになりかけたが(原因はすべて私にある)今では大学院で簿記や会計の講義を担当するようになるなど人生は分からないものである。
検定試験を目標として簿記・会計の知識を修得していくことの利点は、専門分野において必要な一通りの知識を体系的に学ぶことができるという点にあるだろう。試験範囲や難易度に応じたレベル分けがされ、その試験が全国の会場で比較的手軽に受験できる試験であったことは大きな意義があると言える。一口に簿記・会計の勉強を始めるといっても、普通は何から手を付けてよいか分からないだろう。
その点、検定試験の合格を目標に勉強を始めれば、合格に向けて自然と体系的な学習を行う事ができる。そこで会計分野に関心を持てば、さらに難しい内容についてもステップアップすることができる。そのようにして簿記・会計という専門領域の学習のきっかけを与えてきたという意味で、我が国の簿記・会計の知識の普及において各種の検定試験が果たしてきた役割は大きい。
検定試験は実務に役立たない?!
しばしば「会計実務というのは100個会社があったら100通りの実務がある」と言われるように検定試験の内容は、必ずしも実務と直結する内容ばかりではないかもしれない。会計基準や実務上の取扱いが変更され、試験勉強で学んだ内容と実務において求められる内容にズレが生じる場合もある。
一例として挙げれば、従来より簿記の検定試験においては、取引の記録である「仕訳」やそれに伴う項目の集計表である元帳という帳簿への記録は、手書きで出題されていたが、実務においてその作業を手書きでしている会社は、ほぼ存在しないと言ってよいであろう。それらの処理の多くはコンピューターにより自動的に集計されるようになっており、そのための会計ソフトが広く使われているためだ。
しかしながら、その事をふまえて、検定と実務は別物だから検定は実務に役立たないとは言えないであろう。検定の勉強を通じて得た専門知識を通して、簿記・会計的な思考を養えば、制度や実務の変化に対応しやすくなるだろうし、会計ソフトにより業務を行うにしても、自分が行っている作業が一連の会計記録の作成においてどのような役割を果たしているかを知っているか否かで業務の理解度は大きく異なるであろう。
本連載も2 年を過ぎ、私も編集者の対応に慣れてきたつもりである。「編集者対応検定」や「締切延長交渉検定」といったものがあればいい線いくかもしれない。そうは言っても、締切の延長交渉や原稿料の値上げ交渉が成功した試しはなく、編集者からすれば私との交渉など赤子の手を捻るがごとくにお茶の子さいさいと言ったところであろう。残念ながらこの分野については、簿記・会計と異なり検定と実務の間には大きな隔たりがある。そんな事を考えながら今日も編集者からの催促に怯えている。嗚呼、そんな私は会計バカ。
ふるいち・ゆういちろう/専門は非営利組織会計、学校会計、公会計、財務会計。
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら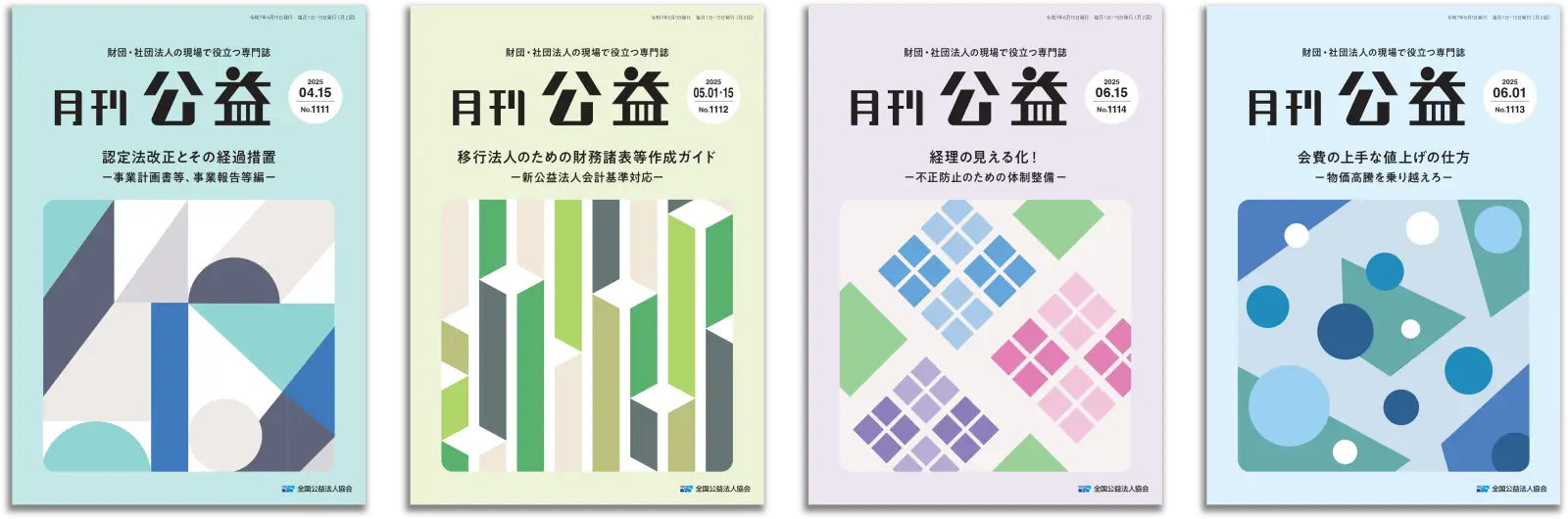
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
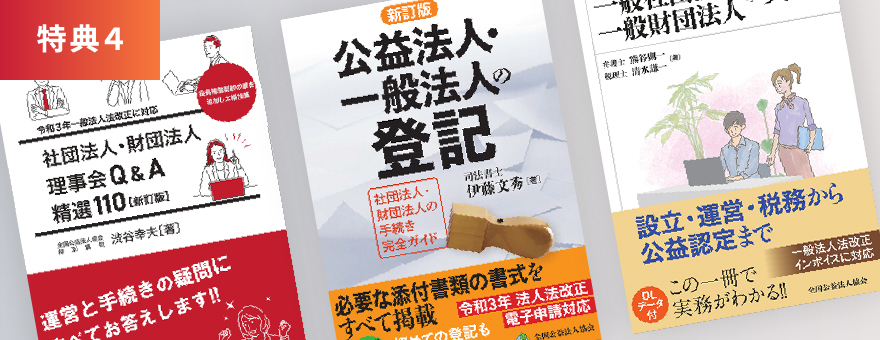
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。