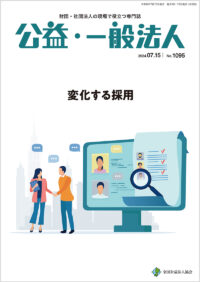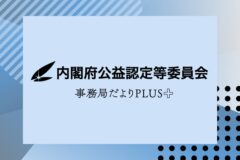【特集】認知症になった理事への対応と留意点
2019年04月19日

渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
厚生労働省によれば、認知症を患う人の数が令和7(2025)年には700万人を超え、65歳以上の5人に1人が認知症に罹患するとのことである。もし、自法人の理事が認知症と疑われた場合、どのように対応すればよいのだろうか。
Ⅰ 認知症・高齢者
認知症とは、記憶などの認知機能(見る、聞く、触れるなどして感じたこと、思い出したり、思いついたりしたこと、その中で大事なこと、目新しいことを見いだして判断し、周りに働きかけ、その反応に適切・柔軟に対応するなどの能力。)(注1)が多方面にわたり障害されるために、日常生活や社会生活に支障をきたす状態とされ、アルツハイマー病や脳血管性認知症など、さまざまな原因によるものが知られている(注2)。総務省統計によると、平成29(20
この記事は有料会員限定です。